Copilot+PCにできることを調べていると、Recall機能やライブキャプション、対応機種やスペック、価格や選び方まで、知りたいことが一気に押し寄せてきて迷ってしまうかもしれません。
どのモデルを買えばいいのか、従来のWindows PCとの違いや、どこまでAI機能が使えるのか、プライバシーや安全性も含めて不安に感じている人も多いはずです。
特に最近は、AI PCやCopilotプラスPCという言葉だけが先行して、「結局、自分の使い方でどこまで便利になるの?」という肝心なところが見えづらいですよね。
公式サイトの説明もスペック表も、それなりに詳しいのですが、日常の仕事や学習のシーンにどう直結するのかは、自分でイメージしないといけません。
このページでは、Copilot+PCとは何かという基本から、実際に何が便利なのか、どんな場面で役立つのかまでを、CopilotプラスPCの具体的な機能一覧や主要なAI機能、対応スペックやCPU、価格帯と選び方のポイントとあわせて整理していきます。
学生や社会人、クリエイターまで、どんな人に向いているのかもイメージしやすくなるようにまとめました。
AI PCとしてのCopilot+PCは、Recallのような画面履歴検索、ライブキャプションによるリアルタイム翻訳、コクリエイターを使った画像生成や編集、Windows Studio Effectsによるビデオ会議の強化など、従来のPCとはひと味違う使い方ができます。
その一方で、CopilotプラスPCが本当に必要かどうか、注意点やデメリットも事前に知っておきたいところですよね。
この記事では、Copilot+PCでできることを一つひとつ丁寧に解説しながら、対応機種や必要スペック、価格の目安、選ぶときのチェックポイントまで、なるべく「自分ごと」として判断しやすい形でお届けします。
- Copilot+PCの基本概要と従来PCとの違いが分かる
- Recallやライブキャプションなど主要AI機能の具体的な使い道がイメージできる
- 対応スペックや価格帯を踏まえて、自分に合うCopilot+PCの選び方を整理できる
- 学生・社会人それぞれのCopilot+PC活用パターンを学べる

読んでいただくことで、あなたにとってCopilot+PCが必要かどうか、どんな使い方が合っているのかが見えてくるはずです。
Copilot+PCにできることを総覧

最初の章では、Copilot+PCでできることを「機能ベース」でざっくり整理しつつ、従来のPCと何が違うのかを体感ベースでイメージできるように解説していきます。
特に、基本機能の全体像から、Recall機能やライブキャプション、コクリエイター、Windows Studio Effectsといった代表的なAI機能を一つずつ見ていきましょう
「なんとなくすごそうだけど、結局なにが楽になるの?」というモヤモヤを、ここで一度クリアにしてしまいましょう。あなたの日常の作業と結びつけながら読んでもらえると、Copilot+PCを買うべきかどうかも判断しやすくなるはずです。
基本機能と特徴で分かる価値
Copilot+PCの一番の特徴は、CPUやGPUとは別にNPU(Neural Processing Unit)と呼ばれるAI専用チップを積んでいることです。
毎秒40兆回以上というレベルの演算を、電力を抑えながらこなせるので、画像生成やリアルタイム翻訳のような重い処理をしても全体の動作がもたつきにくいのがポイントです。
Microsoftも公式に、Copilot+PCは40TOPS以上のNPUと16GBメモリ、256GB SSDを備えた新しいクラスのWindows 11 AI PCだと説明しています。
(出典:Microsoft「Copilot+PC を購入する: Windows AI PC とノート PC デバイス」)
体感として大きいのは、「AI機能を常時オンにしていてもバッテリーが極端に減らない」という点です。
従来のノートPCだと、AI系の処理をクラウドに投げたり、GPUをフル回転させるたびにファンが回ってバッテリーも一気に減りがちでした。
Copilot+PCでは、負荷の高いAI処理をNPUに逃がしながら、省電力で動かす設計になっているので、外出先でも安心してAI機能を使いやすくなっています。
また、OS側の作りもAI前提で最適化されています。
Windows 11に統合されたCopilotは、専用のCopilotキーからワンタッチで呼び出せて、以下のような指示を自然な日本語で投げられるのです。
- 「この資料を要約して」
- 「開いているタブのポイントを整理して」
- 「明日のミーティングのアジェンダを草案して」
CPU・GPU・NPUのどこで処理するかはWindows側が自動で振り分けてくれるので、ユーザーはあまり意識せずに「AIに頼む」感覚で作業を進められます。
Copilot+PCの価値を感じやすいシーン
- 日々のルーティン業務をまとめて時短したいとき:メール処理、議事録作成、資料チェックなど
- 画像・動画・音声を扱う機会が多いとき:簡単な画像生成や写真補正、動画の書き起こしなど
- バッテリー駆動で長時間作業したいとき:カフェや出張先でコンセントを探したくない場合
正直なところ、「Excelやブラウザしか使わない」という使い方であれば、今すぐCopilot+PCが必須とは言い切れません。
ただ、将来的にAI機能を前提として仕事や学習のスタイルを変えていきたいと考えているなら、土台としてCopilot+PCを選んでおく価値はかなり大きいと感じています。
- AI専用のNPUで、画像生成や翻訳などの処理を高速・省電力で実行できる
- CopilotキーからすぐAIアシスタントを呼び出せるので、PC操作全体が「自然な会話」に近づく
- 将来のWindows AI機能の多くがCopilot+PC前提で設計されており、長く使うほど差が出やすい

なお、スペックや対応機能はモデルによって差があるため、正確な情報は公式サイトをご確認ください。
Recall機能で画面履歴を検索

Copilot+PCを語るうえでよく話題に上がるのが、Recall(リコール)機能です。
あなたのPCの画面を時系列でスナップショットとして保存しておき、「先週資料で見た青いグラフを探して」のような曖昧な指示で後から探し直せる、画面履歴検索の仕組みを言います。
検索キーワードが曖昧でも、「あのとき見ていたスライド」「チャットで共有されたURL」などを、視覚的な記憶に近い形で遡れるのが特徴です。
感覚としては、「自分専用の時系列スクリーンショット検索エンジン」がPCの中に入るイメージに近いです。
ブラウザの履歴やファイル名を思い出せなくても、自然な言葉で検索して過去の画面にジャンプできるのは、資料探しのストレスをかなり減らしてくれます。
「あの提案書、どこに保存したっけ?」ということが日常茶飯事な人ほど、インパクトを感じるでしょう。
Recallが活きる具体的なシーン
- 営業・企画職:過去の商談資料や、競合サイトのリサーチ内容を瞬時に呼び出したいとき
- クリエイター:参考に見ていたデザインや配色、タイポグラフィの例を後からまとめて振り返りたいとき
- 学生:オンライン授業のスライドや、調べ物をしていたWebページを時系列で見返したいとき
一方で、プライバシーの観点から仕様には注意点もあります。
現在のRecall機能は原則としてユーザーが明示的にオンにした場合のみ動作するオプトイン機能で、保存したスナップショットはローカル保存・暗号化が前提です。
どこまで保存するか、どのアプリは除外するか、どのタイミングで削除するかなど、細かく設定できるようになっているので、利用する場合は最初に必ず設定を見直しておくのがおすすめです。
また、画面に写った情報は基本的にすべて記録される性質があるため、社外秘の資料や個人情報を扱う場面では、「そもそもその作業をRecallの対象に含めるべきか?」をチームや会社のルールとして決めておく必要があります。
便利さと安全性のバランスを、個人だけでなく組織としてどう設計するかが大事なポイントですね。
- Recallは便利な一方で、画面の内容を定期的に記録する性質上、プライバシー設定の確認が必須
- 業務で使用する場合、社内規程や情報管理ポリシーと矛盾しないか必ず確認する
- 仕様や対応範囲はアップデートで変わる可能性があるため、正確な情報は公式サイトをご確認ください

機能の有効・無効や除外アプリの設定などに迷う場合は、最終的な判断は専門家にご相談ください。
ライブキャプション機能の特徴
もうひとつ、Copilot+PCの注目機能がライブキャプション(Live Captions)です。
ライブキャプション機能は、PCから出ている音声(動画、オンライン会議、ストリーミングなど)をリアルタイムに文字起こしし、さらに別の言語に翻訳して字幕を表示できる機能です。
耳で聞き取りづらい音声や、英語をはじめとした外国語コンテンツを理解するときにかなり心強い存在になります。
特に便利なのは、特定のアプリだけではなく、PC全体の音声を対象に字幕を載せられる点です。
たとえば、ある会議ツールで行われている英語のオンライン会議でも、ライブキャプションをオンにしておけば、そのまま英語字幕や英語に翻訳されたテキストを画面上に出してくれます。
YouTubeやオンライン講座の動画でも、字幕が提供されていない場合に「擬似字幕」として活用可能です。
ライブキャプションの活用パターン
- 外国語の会議・セミナーの理解を助ける:専門用語を聞き逃しても、字幕で確認できる
- 静かな環境での視聴:音量を上げにくい場所でも、字幕で内容を追える
- ノート取りの効率化:重要なフレーズだけ字幕からコピーしてメモに残す
現時点では、多くの環境で「他言語→英語」方向の翻訳が中心で、日本語に対応しないパターンもありますが、アップデートで対応言語が増えていく流れです。
国や地域、Windowsのビルドによって挙動が変わることもあるため、実際に使う前に、自分の環境でどこまで動くかを一度試しておくと安心です。
また、音声認識や字幕の精度は、「マイクの品質」「周囲の雑音」「話者の発音」などに大きく左右されます。
すべての場面で完璧な文字起こしができるわけではないので、「あくまで理解をサポートするツール」と捉え、重要な契約内容や機密情報の確認には元の文書や正式な議事録を必ず併用する、くらいのスタンスがちょうどいいでしょう。

ライブキャプションは、聴覚に不安がある方や、日本語以外のコンテンツにチャレンジしたい方にとっても大きな助けになります。
一方で、「誤認識のリスク」「翻訳のニュアンスのズレ」はゼロにはならないため、重要な箇所は必ず複数の手段で確認するようにしてください。
コクリエイター機能による画像生成活用法
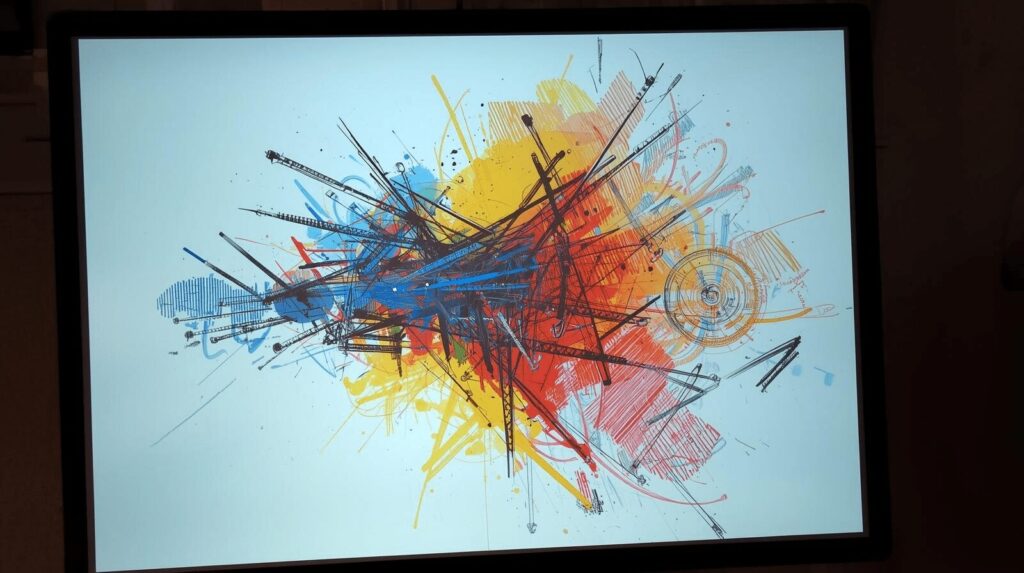
Copilot+PCでは、画像まわりのAI機能もかなり強化されています。
代表例が、ペイントアプリに統合されているコクリエイター(Cocreator)です。
テキストで指示を入力して、イラストや写真風の画像を自動生成したり、元の画像をもとにスタイルを変えるといったことができる機能ですね。
「ブログのアイキャッチをさっと作りたい」「プレゼン資料用のシンプルなイラストが欲しい」といったときに、わざわざ別サービスを開かなくても、Windows標準アプリからAI画像生成が完結するのはかなり快適です。
生成した画像をそのままペイント上で微調整したり、別のアプリにコピペして使えるので、簡単なデザイン作業ならCopilot+PCだけで完結しやすくなります。
コクリエイターでできることの具体例
- 「青い背景にノートPCが置かれたシンプルなイラスト」のような指示で、スライド用のイラストを生成
- 手書きのラフスケッチを読み込んで、色付きのイラストに変換する
- 同じ構図で、色違いやスタイル違いのバリエーションをまとめて作る
このあたりの機能は、デザイナーでなくても恩恵が大きいです。
パワポ用の図版や、社内資料のイメージカットを用意するたびにフリー素材サイトを巡回していた人にとっては、「探す時間」そのものをショートカットできます。
もちろん、プロのデザイナーがラフ制作やアイデア出しに使うのもアリです。
ただし、画像生成AIには著作権や利用規約の話が必ずついてきます。
商用用途での利用条件や、生成画像の取り扱いはサービスや地域によって異なるため、「一般的には大丈夫そう」に見えても、正式な利用条件は必ず公式ドキュメントで確認しておくのが安全です。
特に、クライアントワークや広告素材に使う場合は、社内規程やクライアント側のガイドラインとの整合性もチェックしておきましょう。

プレゼン用のスライド作成を効率化したい場合は、Geminiを使ったスライド自動作成の解説も参考になります。
Geminiでパワポを作成する手順と注意点をまとめた記事と組み合わせると、Copilot+PCと他のAIツールの使い分けもイメージしやすくなるでしょう。
WindowsStudioEffectsのAI機能
リモートワークやオンライン会議が多い人にとっては、Windows Studio EffectsもCopilot+PCの「できること」の代表格です。
Windows Studio Effectsはカメラやマイクに対してAI処理をかけ、背景ぼかしや自動フレーミング、アイコンタクト補正、ノイズ除去などをリアルタイムで行ってくれる機能群をいいます。
もともと背景ぼかしなどは各会議アプリにも搭載されていますが、Copilot+PCではOS側のAI機能として統合されているため、処理が安定しやすく、アプリごとに設定を変えなくても同じクオリティを維持しやすいのがメリットです。
自宅で少し生活感のある背景でも、AIが自然にぼかしてくれるので、カメラオンにする心理的ハードルも下げてくれます。
オンライン会議の印象を変える要素
- 背景:適度なぼかしで「生活感を減らしつつ、完全に違和感のない画」にする
- 視線:アイコンタクト補正で、カメラ目線に近い自然な印象を作る
- 音:キーボード音や環境音をAIノイズ除去で抑え、声をクリアに届ける
マイクのノイズ抑制も、キーボードのタイピング音やエアコンの音など、日常的なノイズをかなり軽減してくれます。
「音と映像のクオリティが整っているだけで、オンラインでの印象は大きく変わる」ので、打ち合わせや商談をよく行う人ほど恩恵を受けやすい機能です。
- オンライン会議の「見え方」「聞こえ方」をAIで底上げできる
- アプリごとではなくOSレベルで機能が提供されるため、設定や挙動が統一されやすい
- 重要な商談や面接など、失敗したくない場面で特に力を発揮する

Studio Effectsの効果はカメラやマイクの物理的な品質にも影響されます。
内蔵カメラの画質に限界を感じる場合は、外付けWebカメラやマイクを導入したうえで、Studio Effectsを組み合わせると、オンライン会議の質が一段と上がるでしょう。
「まずは今の環境で試してみて、足りない部分だけ後から追加する」という順番がおすすめです。
Copilot+PCの選び方とできること

ここからは、Copilot+PCの「できること」を踏まえたうえで、実際にどんなスペックのPCを選べばいいのか、従来PCとの違いをどう見極めるか、といった買う前の判断材料を整理していきます。
対応機種やCPU、メモリやストレージの要件、価格帯の目安、学生・社会人それぞれの活用イメージまで、一気にまとめました。
「今持っているPCでもWindows 11は動いているけど、Copilot+PCに買い替える意味はあるの?」という疑問に、少しずつ答えを出していくイメージで読んでもらえると幸いです。
Copilot+PC対応機種と要件
まず押さえておきたいのが、どんなPCがCopilot+PCとして扱われるのかという点です。
ざっくり言うと、十分なAI性能を持つNPUと、ある程度以上のメモリ・ストレージを備えたWindows 11 PCが対象になっています。
具体的には、NPUの性能が40TOPS以上、メモリが16GB以上、ストレージが256GB以上といったラインが一つの目安です。
代表的なCPU(SoC)の例としては、次のようなシリーズがあります。
| メーカー | 代表的なCopilot+PC向けCPU | 特徴(概要) |
|---|---|---|
| Qualcomm | Snapdragon X Elite / X Plus | 高性能NPUと省電力性に強みを持つArmベースのSoC。バッテリー駆動時間の長さが魅力 |
| Intel | Core Ultraシリーズ(2世代目以降など) | CPU内蔵NPUでAI処理を高速化した最新世代のCPU。従来アプリとの互換性も高い |
| AMD | Ryzen AIシリーズ(300番台など) | CPU・GPU・NPUのバランスに強みがあるAPU構成。グラフィックス性能も重視したい人向け |
メモリは16GB以上、ストレージはSSD 256GB以上が一つの目安になっています。
AI機能を本格的に使いながら複数アプリを立ち上げることを考えると、個人的にはメモリは16GBを「最低ライン」と考えておくと安心です。
クリエイティブ用途や開発用途があるなら、32GB以上も積極的に検討したいところです。
対応機種としては、Surface ProやSurface Laptop、各社の薄型モバイルノート(Yoga、XPS、OmniBookなど)に加え、ビジネス向けのLatitudeやThinkPad Tシリーズなどもラインナップされています。
購入時は「Copilot+PC対応」や「AI PC」といった表示が仕様ページにあるかどうかを必ずチェックしておきましょう。
- 同じシリーズ名でも、CPUやメモリ構成によってCopilot+PCに該当しないモデルがある
- 海外モデルと国内モデルで仕様が微妙に異なるケースもあるため、販売国の仕様ページを必ず確認する
- スペックの詳細や対応機能はアップデートや改良で変わる可能性があるため、正確な情報は公式サイトを確認する

モデルによっては、同じ見た目でもCPU構成によってCopilot+PC対応・非対応が分かれることもあります。
業務用途で導入する場合は、社内の情報システム部門やベンダーとも相談しつつ、最終的な判断は専門家にご相談ください。
従来PCとの違いと注意点

Copilot+PCと従来のWindows PCの違いは、「単に新しいCPUを積んでいるかどうか」だけではありません。
実際に使ううえでは、次のようなポイントが大きな差になってきます。
主な違いのざっくり整理
- AI処理の多くをローカルで完結できる(NPUにより、クラウド依存度が下がる)
- バッテリー持ちが良くなりやすい(AI処理の電力効率が高い)
- RecallやWindows Studio Effectsなど、一部のAI機能はCopilot+PC前提で設計されている
- CPU・GPU・NPUの連携を前提にした最適化が進んでいる(AIを使ってもPC全体が重くなりにくい)
「AIを使うために、いちいちブラウザを開いてクラウドサービスにアクセスする」のではなく、OSレベルでAIが常駐しているイメージに近いです。
何かやりたいことがあったら、とりあえずCopilotに投げてみる。そんな使い方がストレスなくできるのが大きな違いですね。
一方で、注意しておきたい点もあります。
特にArmベースのSnapdragon搭載モデルでは、従来のWindows用アプリがエミュレーション動作になるケースがあり、アプリによっては動作が不安定だったり、機能が制限されることがあります。
対応状況は少しずつ改善されていますが、「必須アプリが問題なく動くか」は事前に確認したほうが安心です。
導入前にチェックしておきたいこと
- 業務で必須のアプリが動くか:会計ソフトや古い業務システムなど
- 周辺機器のドライバー対応状況:特殊なプリンタや計測器など
- 社内のセキュリティソフトやVPNとの相性:新しいアーキテクチャで動作検証が済んでいるか
また、Recallのような新しいAI機能は、地域やWindowsのバージョンによって提供タイミングが異なる場合があります。
「Copilot+PCだから絶対にすべてのAI機能が今すぐ使える」とは限らないので、購入前にサポート情報やリリースノートをチェックしておくのがおすすめです。
- 一部の旧来アプリや周辺機器は、最新環境での動作検証が十分でない場合がある
- AI機能の仕様や提供範囲はアップデートで変わる可能性があるため、定期的な情報収集が必要
- 互換性の検証や移行には時間がかかることもあるため、余裕を持ったスケジュールで導入する

こうしたリスクも踏まえたうえで、正確な情報は公式サイトをご確認ください。
特に法人導入では、最終的な判断は専門家にご相談ください。
価格帯と用途別の選び方
Copilot+PCはハイエンド寄りの仕様ということもあり、どうしても価格帯は従来のエントリーPCより高めになりがちです。
ただ、最近はエントリーモデル寄りの構成も増えてきており、ざっくり次のようなイメージで見ると分かりやすいです。
- おおよそ10万円前後:軽めの事務作業+AI機能を試したいライトユーザー向け
- 15〜20万円台:ビジネス利用や学習+クリエイティブ作業をバランスよくこなしたい人向け
- 20万円以上:動画編集や大規模な画像処理など、重めのクリエイティブ用途もこなしたい人向け
もちろん、上記はあくまで一般的な目安です。
セールやキャンペーンで価格が大きく変動することもありますし、同じ価格帯でもメモリやストレージ、ディスプレイ品質にかなり差があります。
用途別の優先順位の付け方
- 資料作成とオンライン会議がメイン:CPU・NPU性能に加え、カメラとマイク、スピーカー品質を重視
- 画像編集や簡単な動画編集もやりたい:メモリ容量(16〜32GB)とストレージ速度(NVMe SSD)を優先
- 出張や外出が多い:重量、バッテリー時間、充電方式(USB-C対応か)をチェック
選び方のコツとしては、まず「何に一番時間を使っているか」をはっきりさせることです。
また、「今すぐ最大限のスペックが必要か」「2〜3年後の使い方まで見据えるか」によっても、選ぶべきラインが変わってきます。
長く使う前提なら、メモリとストレージはケチらないほうが、後悔しにくいでしょう。
生成AI全体の活用イメージをもう少し広くつかみたい場合は、生成AIの仕組みと活用トレンドをまとめた記事も合わせて読んでおくと、「PC側に求めるスペック」と「クラウド側のAIサービス」の役割分担について整理しやすくなります。
費用対効果を考えるうえでも、「どこまでをPCに任せるか」を意識してみてください。

なお、ここで挙げた価格帯は市場全体のざっくりした傾向であり、厳密な水準ではありません。
正確な価格は販売店や公式ストアでの最新情報を確認し、分割払いなどを含めた総支払額については、最終的な判断は専門家にご相談ください。
学生や社会人の活用機能例

Copilot+PCでできることは、立場やシーンによって見え方が変わります。
この章では、学生と社会人の大きく2パターンに分けて、具体的な活用イメージを整理しました。
「自分の1日の時間の使い方」を思い浮かべながら読んでみてください。
学生の場合:レポートと就活をまとめて効率化
学生にとってCopilot+PCが一番役に立つのは、レポートや卒論などの文章作成と、就活にからむ自己分析・ES作成あたりです。
Copilotや他の生成AIと組み合わせることで、次のようなことがやりやすくなります。
- 授業のスライドや参考文献を要約して、レポートのアウトライン作りに活かす
- 英語論文をライブキャプションや翻訳機能で読み進め、難しい部分だけAIに噛み砕いてもらう
- グループワークのオンライン会議を文字起こしし、終了後に要点だけをまとめた議事録を作る
- PowerPointのスライド構成をCopilotに提案させて、デザインはコクリエイターの画像生成で補う
また、就活のフェーズでは、自己PRのたたき台を複数パターン作ってもらい、自分の言葉に書き換えていく、という使い方も現実的です。
「ゼロから書く負担を減らしつつ、最終的な表現は自分でコントロールする」というバランスを意識すると、AIに頼りすぎずに力を伸ばしていけます。
「AIを学習にどう取り入れるか」の視点はとても大事なので、学生向けに整理した生成AIのメリットを解説した記事も一緒にチェックしておくと、Copilot+PCの活かし方がより立体的に見えてくるでしょう。
社会人の場合:メール・会議・資料作成をまとめて時短
社会人の場合は、毎日のメール処理やオンライン会議、資料作成といった「細かいタスクの積み重ね」をどこまで削れるかがポイントになります。
社会人がCopilot+PCを活用できると考えられるのは、次のような場合です。
- メールボックスをCopilotに要約させ、重要度の高いものから順に処理する
- オンライン会議の音声をライブキャプションで文字起こしし、終了後に要点だけをCopilotに整理してもらう
- 打ち合わせ前に、関連する業界ニュースをAI要約でざっとキャッチアップする
- 会議メモをもとにPowerPointの下書きスライドを自動生成し、あとから自分で肉付けする
営業職なら顧客とのメールやチャット履歴を分析して、「次の提案で押さえるべきポイント」をCopilotに抽出させることもできます。
企画職なら、過去の企画書や市場レポートをまとめて読み込ませて、アイデアのブレインストーミング相手として使うイメージです。
このあたりは、ChatGPTやClaude、Copilotなど複数のAIを使い分けることで、さらに効率が上がります。
- 学生は「学習+就活」、社会人は「メール+会議+資料作成」でCopilot+PCの恩恵を受けやすい
- どちらの立場でも、「ゼロからすべてAIに書かせる」のではなく、「たたき台づくり」と「整理」にAIを使うとバランスが良い
- 費用対効果は使い方次第なので、自分の1日のタスクを紙に書き出してから検討するのがおすすめ

Copilot+PCは「土台としてのPC環境」を整えてくれるので、あとはどのAIをどう組み合わせるか、という発想で考えてもらうのが良いかと思います。
Copilot+PCにできることの総まとめ

最後に、Copilot+PCにできることを改めて整理してみます。
Copilot+PCにできることは、「AIによるPC体験の底上げ」そのものと言ってもよく、具体的には次のようなポイントに集約されます。
- NPUによる高速・省電力なAI処理で、画像生成やリアルタイム翻訳、ノイズ除去などが日常使いできる
- Recallで過去の作業画面を遡って検索できるため、「あのときの資料どこ行った?」を減らせる
- ライブキャプションで、外国語の動画やオンライン会議の内容を字幕ベースで追いやすくなる
- コクリエイターやWindows Studio Effectsで、クリエイティブ作業やオンライン会議の質を底上げできる
- 学生はレポート作成や就活、社会人はメールや会議の効率化など、自分の立場に合わせて「時間の削りどころ」を作りやすくなる
一方で、Armベースのモデルでの互換性や、新しいAI機能のプライバシー設定など、意識しておきたい注意点もあります。
Copilot+PCを検討するときは、「今の自分の仕事や学習スタイルにとって、どの機能が一番効いてくるか」をイメージしながら、スペックや価格、対応アプリの条件を冷静に見ていくのがおすすめです。
AIの機能は今後もアップデートで変化していきます。正確な情報は公式サイトをご確認いただきつつ、費用面や業務での利用ルールなど、不安がある部分は最終的な判断は専門家にご相談ください。
Copilot+PCはあくまで「AIを使いこなすための土台」なので、あなた自身の使い方と組み合わせてこそ、本当の価値が見えてくるでしょう。
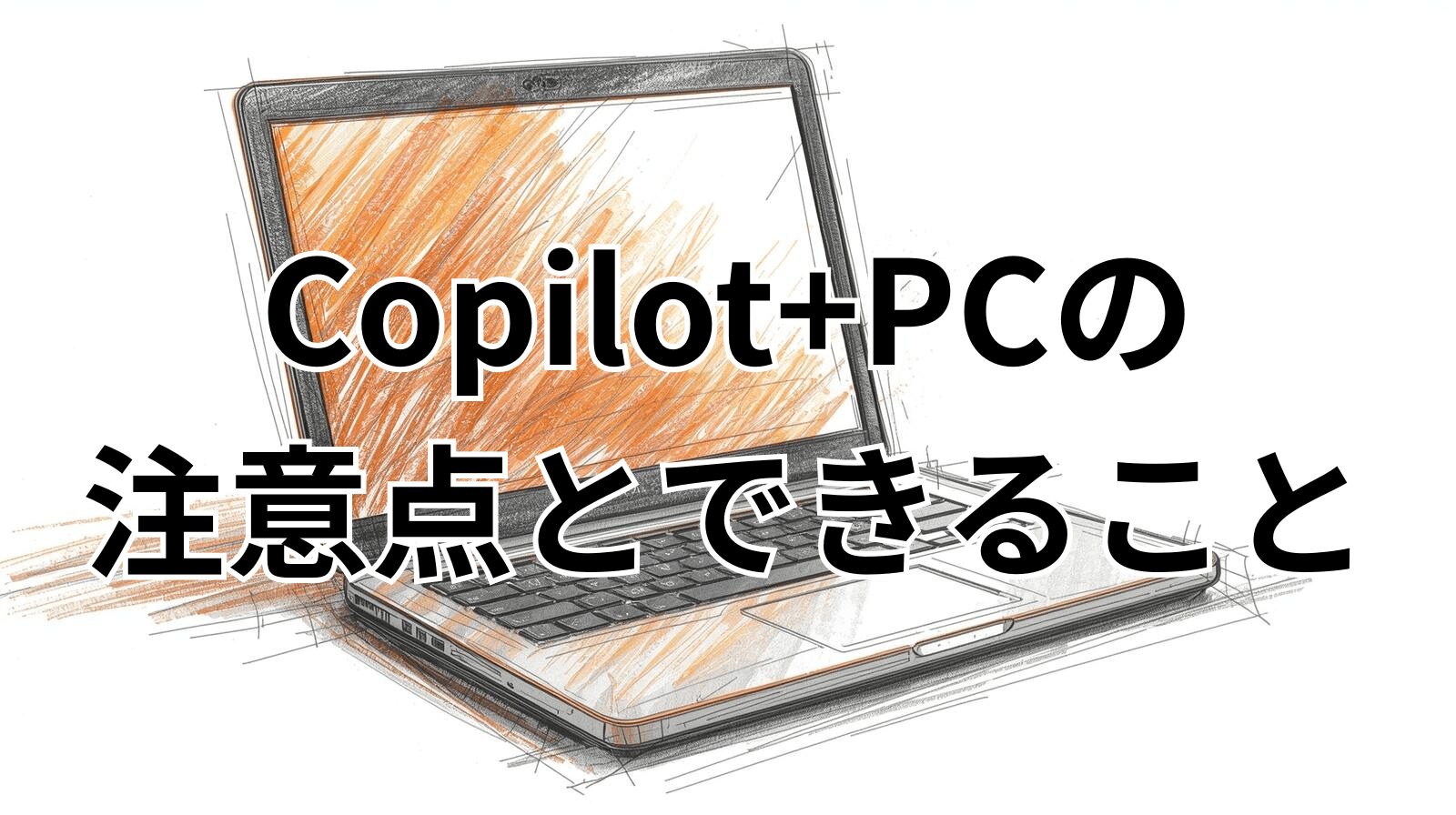





コメント