Copilotの議事録作成プロンプト例を探しているあなたは、たぶん「会議の要点をサクッとまとめたい」「Teamsの自動議事録をもっと使いこなしたい」「録音や文字起こしとどう組み合わせるべき?」みたいな悩みがあるはずです。
ここ、気になりますよね。
私も普段からCopilotで会議メモや要約を回しているんですが、結局のところ成果の差はプロンプトの型に出ます。
対面会議でもオンライン会議でも、議事録の作り方やテンプレートの持ち方、アクションアイテムの抜き出し方が決まってくると、作業時間が一気に縮むんですよ。
この記事では、Copilot議事録作成プロンプト例を軸に、Teams会議のrecap活用、Teams以外の会議、音声データからの議事録化まで、現場でそのまま使える指示の作り方をまとめます。
無料のプロンプトジェネレーターで型を学ぶコツも扱うので、初心者でもすぐ再現できるはずです。
「Copilotで議事録を作らせる」と聞くと、いきなり魔法みたいに全部やってくれるイメージを持つかもしれません。
でも実際は、AIの力をきちんと引き出せるかどうかは、あなた側の“渡し方”で決まります。
会議そのものが同じでも、プロンプトが違うだけで、要点の抜けや粒度のばらつきが驚くほど変わるんですよ。
逆に言うと、ここで紹介する型とコツを先に持っておけば、会議ごとに「今日はどう指示しよう…」と迷う時間がほぼゼロになります。
議事録って地味に時間を吸われがちなので、サクッと自動化して、もっと大事な仕事に集中しちゃいましょう。
- Copilotで議事録を安定生成するプロンプトの型
- Teams会議recapやFacilitatorを前提にした指示例
- 対面・Teams以外・音声データ別の使い分け
- テンプレート化とゴールデンプロンプトの作り方
Copilotの議事録プロンプト例の基本

まずは土台。Copilotに議事録を作らせるときの「プロンプトの設計ルール」を押さえます。
ここが固まれば、どんな会議でもブレない議事録が出せるようになるでしょう。
プロンプトの書き方基本ルール
Copilotで議事録を作るときのプロンプトは、とにかく「目的・出力形式・抽出観点」を一文ずつ明確にするのがコツです。
たとえば「要約して」だけだと、Copilot側の解釈に寄りやすく、会議によって粒度が変わります。
ここを最初に整えるだけで、議事録の“当たり外れ”が激減しますよ。
プロンプトは3つの層で考える
私はいつも次の3層で指示します。
これはCopilotに限らず、どの生成AIでも効く“設計の基本形”です。
- 目的:何のための議事録か(共有/意思決定/後工程の確認など)
- 形式:見出し構造、箇条書き、表など
- 観点:決定事項・論点・宿題・期限・担当など
この3層って、要は「何を、どんな形で、どの切り口で抜くか」を固定するための枠です。
会議ごとに話題は変わっても、議事録に求められる情報の型はそこまで変わらないので、ここを決め打ちしておけば、毎回の指示がラクになります。
Copilotが迷うポイントを先回りする
Copilotは会議ログを“それっぽく”まとめるのが得意なんですが、逆に言うと、あなたが指定しない部分は、Copilotの解釈に委ねられます。
「重要な点をまとめて」と言うと、発言量が多い人の話を重めに拾ったり、雑談っぽいところを要点扱いしたりすることがあるんですよね。
だから、プロンプトでは「重要とは何か」を明確に定義します。
たとえば「決定事項とその理由」「未決事項」「次回までの宿題」のように、あなたが欲しい“議事録としての価値”をそのまま観点に落とす感じです。
私が会議の最初に入れる“定番のひと言”はこんな感じです。
- この会議の目的は◯◯です
- 議題はA→B→Cの順です
- 決定事項・未決事項・次アクションを必ず分けて整理してください
これだけでも、Copilotの要約はかなり締まります。
さらに一発で完璧を狙うより、最初は「短く具体的に→微調整」の対話型で詰める方が結果が安定するでしょう。
議事録は“最初の一投”より“調整の一言”で完成度がグッと上がるので、そこも含めて運用するといいですよ。

なお、会議の内容が機密寄りの場合は、入力する前に必ず社内ルールや契約条件を確認してください。
AIの設定や保存仕様は環境で違うことがあるので、最終判断は公式情報や専門部署に相談するのが安全です。
プロンプトテンプレートで再現性を作る

議事録プロンプトは、テンプレート化した瞬間に強くなります。
理由は単純で、会議は毎回ゼロから考えるより「同じ骨格に流し込む」方が内容が抜けにくいからです。
ここをやるかどうかで、議事録作成のスピードと品質が“別物”になります。
テンプレの中心は「骨格を固定すること」
Copilotの議事録がブレる最大の理由は、会議ごとに「拾うべき情報の枠」が変わってしまうこと。
テンプレートは、その枠を固定するための道具です。
私がよく使う骨格はこの4ブロック。
- 会議の目的・背景
- 議題ごとの要点(論点→結論→根拠)
- 決定事項と理由
- アクションアイテム(誰が/いつまでに/何を)
この構造をプロンプトに埋め込むと、Copilotは自然にその順番で整理してくれます。
逆に構造がないと、要約が流れ書きになって後から使いづらい議事録になりがちです。
会議中は理解できても、1週間後に読み返すと「で、結局何が決まったんだっけ?」ってなるやつですね。
テンプレは“会議の種類ごと”に用意する
テンプレを1個だけ作って全部に使うのもアリなんですが、さらに効率を上げたいなら「会議のタイプ別」にテンプレを分けるのがコツです。
たとえば、定例会なら進捗と課題に寄せるし、意思決定なら選択肢と判断理由を太くする。
これを先にテンプレに仕込んでおけば、会議後に迷う必要がないんですよ。
テンプレを作るときは“理想の議事録の完成形”を先に決めるのが早いです。完成形から逆算して、必要な見出しを固定しちゃうイメージですね。

テンプレは一度作ったら終わりじゃなく、運用しながら磨いていくものです。
実際に使って「ここは毎回いらないな」「この観点が抜けやすいな」と感じたら、サクッとテンプレに反映していけばOK。
こうやって改良を積み重ねると、誰が使っても同じ品質で議事録が作れる状態に近づいていきます。
ゴールデンプロンプトの作り方
ゴールデンプロンプトっていうのは、少ない文で最大の精度を引き出す“勝ちパターン”の指示のこと。
私は次の条件を満たしたらゴールデン認定しています。
- 指示が短いのに、決定事項と宿題が漏れない
- どの会議でも同じ粒度で返ってくる
- 修正依頼がほぼ不要
これ、持っておくと議事録作成が本当に楽になります。
作り方は「削る」作業
ゴールデンプロンプトの作り方はシンプルで、テンプレートを使った後に「不要な語を削っていく」です。
最初は丁寧に書き、うまく出たら効いた部分だけ残す。
これを3〜5回やると、驚くほど短いプロンプトに圧縮できます。
たとえば最初は、目的も形式も観点も全部フルで書きます。
そこで出力が安定したら、目的の説明を1行に縮める、形式の説明を「箇条書きで」とまとめる、観点を固定語化する、みたいに削っていく感じですね。
これが進むほど、議事録の“回転率”が一気に上がります。
ブレたら「観点」と「入力」を疑う
なお、出力がブレたときは「抽出観点の不足」か「入力側の情報の欠落」が多いです。
観点をひとつ足すと改善するケースは多いし、会議ログの前処理(ノイズ除去、話者分離、議題ごとの区切り)を見直すと一気に安定します。
ゴールデン化のコツは、プロンプトの“固定語”を作ること。
- 決定事項=必ず抽出
- 未決事項=必ず抽出
- 次アクション=担当者と期限つき

この固定語がプロンプトに入っているだけで、Copilotは「ここが外せない要素なんだな」と理解しやすくなります。
短いのに強い指示って、こういう“芯”が入っているんですよ。
プロンプト一覧の作り方と管理
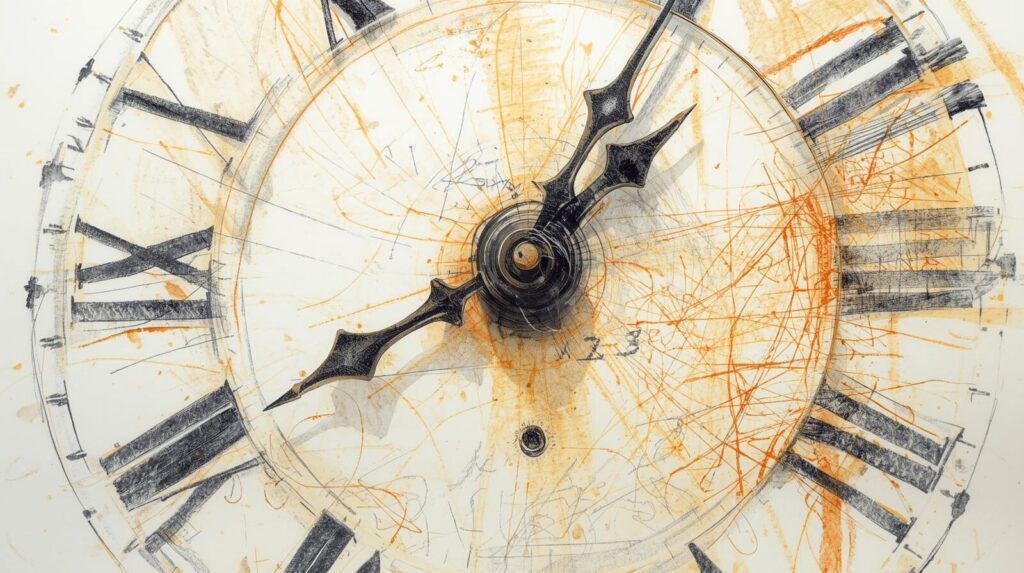
現場で効くのは「用途別プロンプト一覧」を持つことです。
私はNotionや社内Wikiに、会議のタイプ別に“すぐコピペできる指示”を並べています。
ここがあると、会議後の処理がほぼルーティン化しますよ。
一覧は「迷いを消すための棚」
私は次のようなカテゴリで整理しています。
- 定例会議用(進捗・課題・次週方針)
- 意思決定会議用(論点→選択肢→結論→理由)
- 顧客同席会議用(要望・合意事項・次回アクション)
- 1on1用(本人の発言要約+支援案)
一覧化のメリットは「迷わず投げて、同じ品質で返す」こと。
議事録って、担当者が変わるだけで粒度や書きぶりが変わりがちじゃないですか。そこを一覧で吸収しちゃう感じです。
チームで使うなら、テンプレと一覧をセットで共有した方が、議事録の品質が担当者依存にならずに済みます。
管理の基本は「更新しやすさ」
一覧は作って終わりじゃなく、定期的なメンテが前提です。
会議の進め方が変わったり、成果物のフォーマットが変わったりすると、プロンプトも微妙にズレます。
だから、一覧は「誰でも更新できる場所」に置くのが鉄則。NotionやLoop、社内Wikiあたりが相性いいですね。

“改善ログ”を一緒に残すと、チーム内で上達が早いです。
「この一文を足したら精度が上がった」みたいなメモを残してみましょう。
プロンプトジェネレーターの使いどころ
無料のプロンプトジェネレーターは、ゼロから型をつくるときの学習用に便利です。
私も最初の頃は、ジェネレーターが吐いたプロンプトを分解して「どこで条件付けしているか」「なぜこの順番なのか」を観察してました。
これ、地味だけど上達スピードが上がります。
ジェネレーターは“答え”より“教材”
大事なのは、生成された指示をそのまま使うことじゃなく、構造を盗むことです。
ジェネレーターが「目的→条件→出力形式」の順で書いていたら、その順番がAIに通りやすいんだな、と学べる。
複数のツールを触ると、共通する“勝ち型”が見えてくるんですよ。
無料ツールの落とし穴も理解しておく
ただし、無料ツールで生成した指示をそのまま業務に貼るのは注意が必要です。
保存・共有・商用利用の扱いや、入力データの保持ポリシーはツールごとに違います。
特に企業利用だと、入力した内容が学習に回る設定になっていないか、サーバーがどこにあるのか、など細かい違いがリスクに直結します。
社内情報や顧客情報を入力する前に、必ず利用規約とセキュリティ方針を確認してください。
この一手間で、あとから面倒なトラブルを避けられます。

最終的な運用判断や規約の解釈は、必ず公式サイトの記載をご確認ください。
社内ルールや契約に関わる場合は、必要に応じて法務・情報システムなど専門部署に相談するのが安全です。
Copilotの議事録作成プロンプト例の活用シーン

ここからは実戦編。
会議の形態ごとに、Copilotへどう指示を出すとラクに高品質な議事録が出るかを整理します。
議事録対面会議での使い方
対面会議は、オンラインと違って自動トランスクリプトがないケースが多いので「入力の作り方」がキモです。
方法は大きく2つあります。
ここを押さえるだけで、対面でもCopilot議事録が普通に戦力化しますよ。
- 会議後にメモや要点をまとめてCopilotへ投入
- 音声を録音→文字起こし→Copilotで整形
対面は「背景」と「順序」を先渡しする
対面のときほど、プロンプト側で「会議の目的」と「議題の順序」を最初に渡すと精度が上がります。
背景がないと、Copilotが重要度を正しく判断しにくいからです。
オンラインのトランスクリプトは会話の流れからAIが推測できる部分もあるんですが、対面メモは情報が圧縮されてるので、推測余地が増えちゃうんですね。
私の対面運用:2段階で回す
私は対面は「会議目的+議題リスト+粗メモ→要点整理→決定/宿題抽出」の2段階で回します。
1段目で要点、2段目でアクションを抜くと漏れを減らせるのです。
いきなり全部やらせると、要約とアクション抽出が混ざって、アクションが薄くなることがあるので、段階を分けた方が安定します。
- 会議目的と議題順を明記
- 粗メモは議題ごとに区切って貼る
- まずは要点だけ抽出させる

この要点が出たら、次に「決定事項/未決事項/次アクションを抜いて」と再プロンプト。
これで、対面でも十分実務レベルの議事録が作れます。
Copilot teamsで使える議事録プロンプト例

Teams会議では、録音と文字起こしがある状態でrecapを開き、Copilotに追加指示を出すのが鉄板です。
TeamsのFacilitatorやrecapの仕組みでは、会議中〜会議後にAIメモや要約が生成され、そこへあなたが“切り口”を加えることで議事録の完成度を上げられます。
(出典:Microsoft Support『Facilitator in Microsoft Teams meetings』)
recap前提なら「議題単位の構造」を指定
私はrecap前提だと、こんな感じで投げます。
会議の文字起こしを前提に、議題ごとに「結論/理由/未決事項/次アクション」を箇条書きで整理してください。
最後に担当者と期限つきのアクション一覧を作ってください。
ここで重要なのは、recapがすでに“会議全体の要約”を持っているので、あなたが追加するのは「どう整理するか」という構造指定だという点です。
会議中に一言足すと後処理が激減
Facilitatorを使っている場合は、リアルタイムで共同編集できるノートが残るので、会議中は「論点が変わったタイミングで短い補足指示」を入れると、後処理がさらに軽くなります。
たとえば「今の議題はAです。Aの結論と根拠を整理して」と一言入れるだけで、あとからrecapを整える作業がほぼ不要になります。
またTeamsの強みは、話者分離やタイムラインが比較的整っている点です。
だからこそ、プロンプトは“重心をどこに置くか”を明確にすると効きます。
意思決定会議なら「選択肢と判断理由」に寄せる、定例なら「次週の方針とリスク」に寄せる、みたいな感じです。

Teamsの場合、会議の録音・文字起こしのON/OFFで精度が大きく変わります。
会議前に設定を確認しておくと、後の議事録が本当にラクになります。
Teams以外の会議における議事録対応
ZoomやGoogle MeetなどTeams以外でも、やることは同じです。
ポイントは「文字起こし精度の差をプロンプトで吸収する」こと。
ここが分かると、どの会議ツールでもCopilot議事録が普通に回せます。
ツールごとの“癖”をプロンプトで補正する
たとえばZoomの自動字幕は話者名が曖昧になりやすいので、プロンプトで「話者ごとの主張の違い」「合意に至った理由」を明確に抜かせると、議事録の価値が上がります。
Google Meetの文字起こしも、専門用語や固有名詞が崩れることがあるので、そういうときは「不明瞭な語はそのまま引用し、推測しない」と一言入れると安全です。
文字起こしがないなら“対面ルート”へ
もし文字起こしがない場合は、対面と同じく「議題リストと粗メモ」を先に渡してから整形させるのが安定ルートです。
ここで無理に“会議を再現させる”より、“あなたが持っている情報で構造を作らせる”方が、結果として正確で使いやすい議事録になります。
- 文字起こしの粗さを前提に観点を明確化
- 話者名が曖昧なら主張の整理に寄せる
- 誤認しやすい箇所は推測禁止を指定

会議ツールが違っても、結局は「目的→形式→観点」の3層を守れば、出力は自然に安定してきますよ。
議事録音声データから作る手順

音声データがある場合は、まず文字起こしを作ってからCopilotに渡す流れになります。
ここは手順を分けた方が成功率が上がります。
ざっくり言うと“前処理で8割決まる”タイプの作業ですね。
- 音声→文字起こし(可能なら話者分離)
- 文字起こしを「議題単位で区切る」
- Copilotで要点・決定事項・宿題を抽出
- 必要なら再プロンプトで整形
音声→文字起こしの段階で勝負がつく
文字起こしが荒いと、それだけでCopilotの要約が崩れます。
特に対面録音だと、環境音や被り発言が多く、話者の切り替わりが曖昧になりやすい。
だから、できる範囲でいいので「話者分離」と「ノイズの少ない環境」を意識すると、後のコストが一気に下がります。
推測させないのが“議事録としての正義”
文字起こしが荒いときほど、プロンプトで「不明瞭な箇所は推測せず、不明として残す」と指定します。
推測させると、会議記録としての信頼性が落ちるからです。
議事録って“それっぽさ”より“事実ベース”が命なので、ここは割り切った方がいいです。
音声データは個人情報や機密を含むことがあります。
保存先、共有範囲、AIへの入力可否は必ず公式情報や社内ルールを確認してください。
最終的な判断は専門部署に相談するのが安全です。

この流れに慣れると、1〜2時間の会議でも、議事録の後処理はほぼ自動で回るようになりますよ。
まとめ:Copilotの議事録プロンプト例で時短を実現
Copilotの議事録プロンプト例の「勝ち筋」は、プロンプトを書き足すことじゃなくて、型を作って再利用することです。
テンプレートで再現性を作り、ゴールデンプロンプトに圧縮し、用途別のプロンプト一覧で迷いを消す。
これだけで、議事録作成の体感コストはかなり下がります。
TeamsならrecapやFacilitatorを前提に切り口を指定する、対面やTeams以外なら入力の作り方を工夫する、音声データなら前処理を分ける。
状況ごとに手順を変えるだけで、Copilotの出力が一気に“実務レベル”に寄ってきます。
あと、地味に効くのが「会議前に“これ議事録に残したい観点”を自分で決めておくこと」。
観点が決まっていると、プロンプトも短くなるし、出力の精度も上がります。
会議のゴールをあなたが握っておくと、Copilotはそこに合わせて整理してくれるんですよね。
- まずはテンプレを1つ作る
- 3回使ってムダ文を削りゴールデン化
- 会議タイプ別に一覧化して共有
最後にもう一度だけ。
ツール仕様や利用規約、データの扱いはアップデートされることがあるので、運用前に公式情報の確認は必須です。
チーム導入や社外秘情報を扱う場合は、社内の専門部署と相談しながら進めましょう。
あなたの現場に合う形で、無理なく“議事録の自動化ループ”を作っていけばOKですよ。



コメント