PlaudNoteの情報漏洩・セキュリティの実態と安心して使うコツ
PlaudNoteの情報漏洩が本当に大丈夫なのか、セキュリティや安全性が気になって検索してくれたのだと思います。
特に、PlaudNoteの情報漏洩リスクやPlaudNoteのセキュリティ、PlaudNoteの安全性、デバイス紛失時の影響、どこの国のサービスかといった点は、気になるところですよね。
実際に、AIボイスレコーダーはクラウド処理や外部AIとの連携も行うので、PlaudNote情報漏洩リスクがゼロとは言い切れません。
一方で、暗号化やアクセス制御など、一定レベルのセキュリティ対策がしっかり作り込まれているのも事実です。
サービス側の仕組みを正しく理解しないまま「なんとなく怖いから使わない」と決めてしまうのはもったいないですし、かといって仕組みを知らずに使い倒すのも危うい、そんなバランス感が求められるところかなと思います。
この記事では、実際にどんな仕組みでデータが扱われているのか、どこに情報漏洩のポイントがあるのか、そしてどう使えば現実的に安心できるのかを整理していきます。
ここを押さえておけば、「PlaudNoteは危ないのでは?」というモヤモヤをかなりスッキリさせられるはずです。
- PlaudNote情報漏洩リスクの現実的な中身と限界
- クラウドと端末それぞれのセキュリティ仕組み
- 機密情報や企業利用で気をつけるべき具体的なポイント
- PlaudNoteをおすすめできる使い方と避けたほうがよい場面
PlaudNoteの情報漏洩の不安と実際

PlaudNoteの情報漏洩について語るときは、まず「そもそもどんなサービスで、どんな経路でデータが動くのか」を押さえておくことが大事です。
この章では、PlaudNoteの基本的な安全性、クラウドと端末ごとのセキュリティ、運営している会社がどこの国に関係しているのかといった、土台となる部分を整理していきます。
難しい専門用語はできるだけかみ砕いていくので、セキュリティに詳しくないあなたでも、最後まで読めば自分なりの判断軸を持てるようになるはずです。
PlaudNoteの安全性を整理する
PlaudNoteは、カード型のAIボイスレコーダーで、録音から文字起こし、要約、マインドマップ生成までをワンタップでこなすデバイスです。
録音は本体で行い、その後スマホアプリやWeb経由でクラウドと連携しながらAI処理を行う、いわゆる「ハードウェア+クラウド+AI」の構成になっています。
見た目はシンプルでも、裏側では複数の仕組みが連携して動いているイメージですね。
安全性という意味では、ざっくり次の三層で考えると整理しやすいです。
- デバイス(PlaudNote本体)側での録音データの扱い
- スマホやPCアプリに保存されるデータ
- クラウド側(AWSなど)にアップロードされたデータ
まず、PlaudNote本体はあくまで「録音の入り口」です。
録音データは一時的に本体に保存されますが、スマホアプリと接続して同期すると、アプリ側へ転送された後に本体からは自動削除される設計になっています。
この仕組みによって、万が一本体そのものを落としてしまっても、過去の録音データが丸ごと残っている可能性はかなり低く抑えられています。
次に、スマホやPCアプリ側です。
こちらは、あなたが日常的に触る「メインの作業環境」になります。
文字起こし結果や要約、タグ付けなどのメタ情報も含めて、アプリ内にどんどん蓄積されていくイメージです。
クラウド同期をオフにしている場合、この段階が実質的な「最終保存場所」になります。
言い換えると、アプリが入っているスマホ・PCのセキュリティレベルが、そのままデータ全体の安全性を左右するとも言えます。
最後にクラウド側。
クラウド同期をオンにすると、録音や文字起こしデータが、暗号化された状態でPlaudのクラウド環境に保存されます。
これにより、複数デバイスから同じデータにアクセスできるようになり、デバイスを買い替えたときにもデータを引き継ぎやすくなります。
一方で、「インターネットの向こう側にデータを置く」という意味では、オンプレミスよりも法制度やサービス側の運用に依存する度合いが高くなる点は理解しておく必要があります。
ここまでをまとめると、「安全かどうか」は製品の仕組みだけで決まるものではなく、以下の3つの掛け算で決まります。
- 本体・アプリ・クラウドという三層構造
- あなた自身の端末管理やパスワード管理の丁寧さ
- どのレベルの情報をPlaudNoteに乗せるかという線引き
極端な話、どんなにセキュリティの高いサービスを選んでも、スマホに画面ロックをかけていなければ、一気にすべて台無しになるんですよね。

PlaudNoteの安全性を考えるときは、「本体だけ」でなく、端末+クラウド+運用ルールの三点セットで見るのがポイントです。
ツールの機能と、自分たちの使い方をセットで設計していくイメージを持ってもらえると良いかと思います。
クラウドと端末のセキュリティ
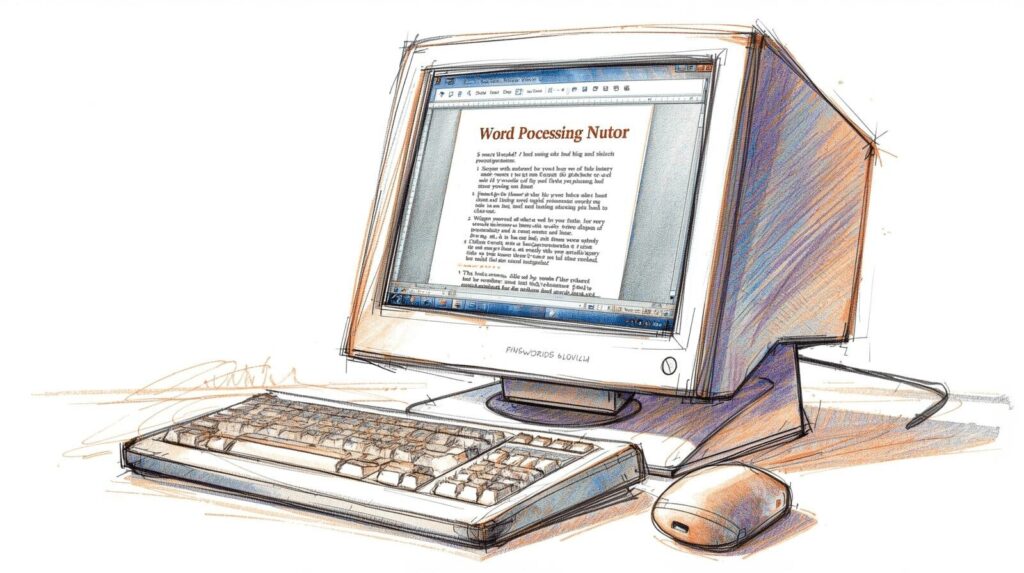
PlaudNoteで録音した音声や文字起こしデータは、設定次第でスマホアプリ内だけに保管することもできますし、クラウドと同期して複数デバイスからアクセスすることもできます。
「どちらを選ぶか」で、セキュリティ上のメリット・デメリットも変わってくるので、このあたりはしっかり押さえておきたいところです。
クラウド側のセキュリティイメージ
公式情報や各種ドキュメントによると、アップロードされたデータは大手クラウド基盤(たとえばAWSなど)上で暗号化された状態で保存され、通信経路もTLS(https)で保護されています。
保存時にはAES-256といった業界標準の暗号化方式が使われ、転送中も第三者が内容を盗み見しにくい構造になっています。
さらに、Plaudはセキュリティ関連の認証(ISOやSOC2など)の取得や、GDPRなどの国際的なプライバシー規制への準拠も進めており、「最低限のライン」ではなく、企業利用を前提にした水準を意識していることがうかがえます。
詳しい項目や技術的な説明は、メーカーのデータセキュリティポリシーにまとまっているので、一度は目を通しておくと安心です。
(出典:PLAUD「Data Security and Privacy Policy」)
とはいえ、クラウドにデータを置く以上、「絶対に漏洩しない」と言い切れるサービスは存在しません。
ゼロリスクを目指すのではなく、「どの程度までリスクを許容できるか」「どんな運用でリスクを減らすか」を考えるのが現実的です。
端末側の弱点は「スマホ紛失」
現実に起きやすいのは、PlaudNote本体そのものよりも、PLAUDアプリを入れているスマホや、Web版にログインできるPCの紛失・盗難です。
画面ロックが甘かったり、ブラウザにパスワードを保存したままだと、クラウドに同期されている録音データまで一気に見られる可能性があります。
特に、ブラウザの「パスワード自動入力」に頼りすぎていると、端末を触られた時点でアカウントも一緒に乗っ取られてしまうリスクがあります。
スマホ・PC側で最低限やっておきたいのは、以下のあたりです。
- 画面ロック(PIN・パスコード・生体認証)の有効化
- OSやアプリのアップデートをこまめに適用すること
- 公共のPCや共有PCからはPlaudアカウントにログインしないこと
- パスワードマネージャーを使い、使い回しパスワードをやめること
どれも地味ですが、これだけで現実的なリスクはかなり下がります。
逆に言うと、ここをサボると、どんなにクラウド側が堅牢でも情報漏洩は普通に起こり得ます。
「セキュリティがしっかりしたサービスを選んだから安心」という感覚は危険で、スマホやPCのロック・パスワード管理をサボると、どんなにクラウドが堅牢でも情報漏洩は普通に起こります。
自分たちの手元の対策とセットで考えるのが大事ですよ。

このあたりはPlaudNoteに限らず、あらゆるクラウドサービス共通の落とし穴だと考えてもらうとイメージしやすいと思います。
PlaudNoteはどこの国の企業か
情報漏洩の議論でよく出てくるのが、「このサービスはどこの国の法律の影響を受けるのか?」という視点です。
PlaudNoteの運営会社はアメリカで登記されていて、本社はサンフランシスコ。
一方で、ハードウェア製造は中国・深圳の企業が担っており、開発拠点も米国・シンガポール・深圳・東京など複数に分かれています。
グローバルに展開している分、いろいろな法制度の影響を受けるポジションにいるサービスと言えます。
この構造から、「中国拠点が関わっている=中国政府にデータが抜かれる」という極端な心配をされる方もいますが、公開されている情報ベースでは「実際にそういう事例があった」という話までは出ていません。
とはいえ、中国を含む複数国が関わる以上、法制度的なリスクが他サービスより増えるのは事実なので、そこをどう許容するかはユーザー側の判断が必要です。
ここで大事なのは、「どこの国か」そのものよりも、「どの法律と規制の組み合わせで守られているか」です。
たとえば、以下のような観点ですね。
- EU圏向けにはGDPRに準拠しているか
- 日本の個人情報保護法にどう対応しているか
- 医療や金融など、業界ごとの規制に耐えうるか
Plaudは自社サイトでGDPRコンプライアンスやISO規格、SOC2などへの対応状況を公開しており、「どのルールの枠組みの中でサービスを設計しているか」をある程度読み取ることができます。
どこの国のサービスかを気にするのは、セキュリティというより「万が一問題が起きたとき、どの法律と管轄で勝負することになるのか」を理解するための視点だと考えてもらうといいかと思います。特に企業利用では、この観点はかなり重要です。

個人利用のあなたにとっては、「このサービスを使った場合、自分のデータはどの国のルールのもとで扱われるのか」というイメージが持てていれば十分です。
一方で、企業として導入する場合は、法務部門や情報セキュリティ部門と連携し、自社の拠点や顧客の所在地も踏まえたうえでリスク評価を行う必要があります。
PlaudNoteにおけるAIの学習とデータ利用
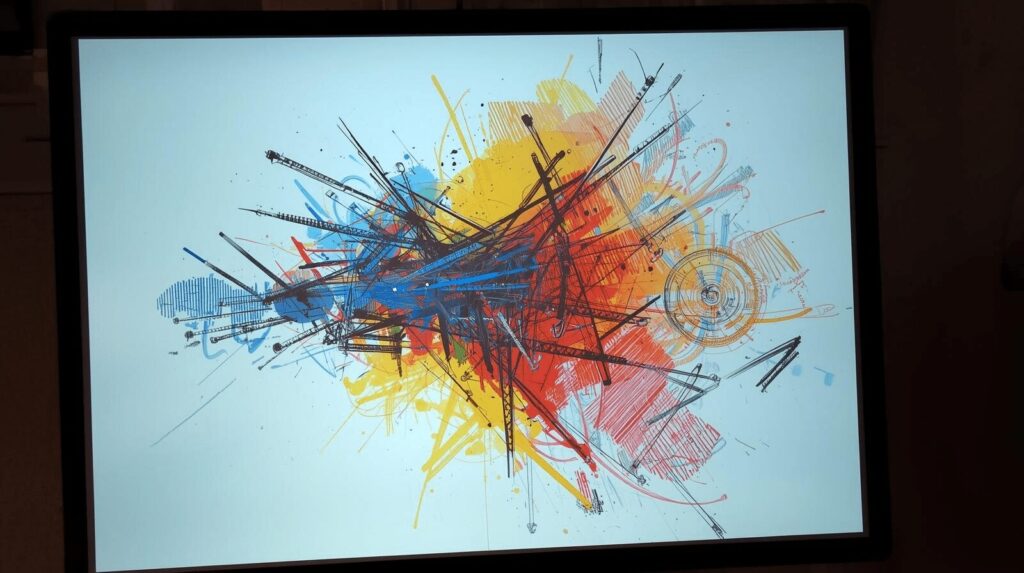
次に気になるのが、「録音したデータがAIモデルの学習に使われてしまわないか?」という点です。
ここはあなたも一番モヤモヤしやすいところだと思うので、できるだけ丁寧に整理していきますね。
OpenAI側の学習利用について
PlaudNoteでは、音声認識や要約にOpenAIなどの外部AIを利用しています。
ただし、OpenAIのAPI経由で送られるデータについては、「ユーザーが明示的に許可しない限り、モデルの学習には使われない」という方針になっています。
これはOpenAIの公式ドキュメントにも明記されていて、API利用とChatGPTなどのコンシューマサービスはポリシーが分かれている形です。
もちろん、「一切保存されない」という意味ではなく、不正利用や障害対応のために一定期間ログとして保持されることはありますが、そのデータが自動的にAIモデルの学習データセットに組み込まれていく、というイメージではありません。
このあたりも、最新の情報はOpenAIの公式ドキュメントで随時更新されているので、気になる場合は原文をチェックしておくとより安心です。
PLAUD側でのデータ活用可能性
一方で、PLAUD側のプライバシーポリシーを読むと、「サービス改善のために統計的・匿名化された形でデータを利用することがある」といった文言は含まれています。
これは多くのSaaSでもよくある書きぶりですが、以下のような細かい部分は、ユーザーからは見えにくいのも事実です。
- どこまでを「匿名化」とみなしているのか
- 録音内容そのものを再利用するのか、メタデータ中心なのか
- どの範囲の社員や委託先がアクセス可能なのか
ここにモヤモヤを感じる方が多いのは、すごく自然な反応だと思います。
私のスタンスとしては、「AI学習に使われるかどうか」が完全にクリアではない限り、機密情報はPlaudNoteに乗せない、という線引きをおすすめしています。
これはPlaudに限らず、あらゆるクラウドAIサービス共通の考え方です。
とはいえ、一般的な会議や営業商談、社外向けセミナーの記録など、多くのビジネスシーンでは、リスクと利便性のバランスを取ったうえで十分に「使える」ラインにあると感じています。
実務的には、以下のようなルールを社内で共有しておくと、迷いにくくなりますよ。
- 録音前に相手にAI処理を含む録音であることを説明して同意を得る
- 扱う情報の機密度をあらかじめレベル分けしておく
- 機密度が高いレベルについてはそもそもPlaudNoteを使わない

このあたりの最新のポリシーは、PLAUD公式サイトのプライバシーポリシー・利用規約を直接確認したうえで判断してください。
最終的な判断に迷う場合は、社内の情報セキュリティ担当や専門家にも相談してもらえると安心です。
機密情報を扱う際の注意点
PlaudNote自体のセキュリティ水準と別に、「機密情報を扱う場面でどう使うか」は、ユーザー側の運用ルールが9割と言ってもいいくらい重要です。
ここを間違えると、どんなに技術的な対策が優れていても、一気にリスクが跳ね上がってしまいます。
PlaudNoteで録音しないほうがいいケース
まず、「これはPlaudNoteで録音しない方がいい」という典型的なケースから整理してみます。
- 未発表のM&Aや大型投資など、株価に直結する情報
- 機微性の高い個人情報(病歴、給与、家庭事情など)が大量に含まれる会話
- 顧客のクレジットカード情報やマイナンバーが読み上げられるような場面
- 契約上「録音禁止」「クラウド保存禁止」とされている会議や面談
このレベルの情報は、そもそもどんなクラウド録音サービスでも「録音しない」が基本です。
PlaudNoteだからNGというより、「クラウド+外部AIに乗せない」という線引きとして考えてください。
たとえば、弁護士や医師など、厳しい守秘義務が課される職種では、そもそもデジタル録音を禁じている組織も少なくありません。
現実的にPlaudNoteを活かしやすい場面
逆に、「ここならPlaudNoteを積極的に活用しやすい」という場面もたくさんあります。
- 社外向けセミナー・勉強会・ウェビナーの記録(録画公開前提の内容など)
- 社内の定例会議やプロジェクトミーティングの議事録作成
- ライター・ブロガー・研究者のインタビュー録音
- 社内勉強会やナレッジ共有会の記録
こういった場面では、PlaudNoteの文字起こしや要約機能が生産性を大きく押し上げてくれます。
録音前に参加者へ録音とAI利用の旨を伝え、同意をきちんと取っておくこともお忘れなく。
録音許可を取る一言があるだけで、後から「そんなつもりじゃなかった」というトラブルを防ぎやすくなります。
要するに、「日々の業務や学習で扱う一般的な情報」にはどんどん使っていく、一方で「これだけは絶対に漏らせない情報」はそもそもクラウドに上げない、という線引きが現実的な落としどころです。

ここをチームで共有しておくだけでも、セキュリティレベルはかなり変わりますよ。
PlaudNoteの情報漏洩対策と結論

ここからは、PlaudNote情報漏洩への世の中の評判や、他のボイスレコーダーとの比較、実際に「使えない」のかどうかという率直な話、そして企業利用で押さえておきたいチェックポイントをまとめていきます。
最終的に、PlaudNoteをどう位置づけてどう使うのが現実解なのかを、一緒に整理していきましょう。
PlaudNoteの情報漏洩における評判
ネット上でPlaudNote情報漏洩を検索すると、「危ない」「やや危険」といった強めの言葉も目に入ってくると思います。
一方で、「きちんと仕組みを理解して使えば問題なく便利」というポジティブなレビューも多く、評価は割れがちです。
どちらの意見もそれなりの根拠があるので、「どっちが正しいか」というより、「自分はどこまで許容できるか」を考える材料にするのが大事だと思います。
実際の論点を整理すると、だいたい次のような声に分かれます。
- 暗号化やクラウドのセキュリティ体制、認証取得などは十分という評価
- 中国拠点や複数国の法制度が絡む点に不安を感じるという声
- AI学習への利用範囲が完全には見えない点へのモヤモヤ
- それでも日常的なビジネス用途には十分実用的という利用者の実感
個人的には、「不安を感じるのは自然だけれど、その不安の中身を分解すると、かなりの部分は運用でコントロールできる」と感じています。
以下のような工夫をすれば、世の中で言われている「やや危険」といった評価も、かなり現実的なラインまでコントロールできるはずです。
- 録音する会議の種類を限定する
- クラウド同期を使う場面と、ローカル完結で使う場面を分ける
- チーム内での運用ルール(録音前の説明やデータ削除のタイミング)を明文化する
私は、こうした評判を踏まえても、「きちんとリスクを理解したうえで使うなら、おすすめできるボイスレコーダー」という立ち位置でPlaudNoteを見ています。
ツールを怖がるのではなく、賢く付き合っていくイメージですね。

大事なのは、「危ないか安全か」の二択ではなく、どのレベルの情報までなら自分や自社として許容するのか、というラインを決めておくことです。
そこさえ決まっていれば、PlaudNoteに限らず、他のAIツールとも落ち着いて付き合えるようになりますよ。
他社レコーダーとの比較視点

他社のAIボイスレコーダーや、スマホアプリ単体の文字起こしサービスと比べたとき、PlaudNoteのセキュリティ面での特徴は次のあたりです。
ここを押さえておくと、「PlaudNoteだから特別に危険」「逆に絶対安全」といった極端な見方から離れやすくなります。
PlaudNote側の特徴
- 専用ハードウェアがあるので、録音時にスマホを触らなくてよい(スマホ操作による情報漏洩リスクを減らせる)
- 録音後はアプリ側に転送され、本体から自動削除される設計
- クラウド同期をオフにして「端末完結型」としても使える柔軟性
- NotePinはAppleの探す機能と連携して紛失対策がしやすい
このあたりは、「録音機器としての安全性」を意識した設計になっていると感じています。
特に、クラウド同期が任意であること、本体にデータを長期間残さないことは、紛失リスクを考えるうえで大きなポイントです。
一般的な比較のポイント
どのサービスを選ぶにしても、セキュリティ観点で比較するなら、次のようなポイントをチェックしておくと良いですよ。
- クラウド保存の有無・範囲(常にクラウドか、任意か)
- 外部AIとの連携状況と、データが渡る先の数
- セキュリティ認証やプライバシー規制への準拠状況
- 端末紛失時にどこまで被害を抑えられる設計か
- 運営会社の透明性(ポリシーや技術情報をどこまで公開しているか)
「どのサービスが絶対安全か」というより、自分の用途に対してどのリスクなら許容できるかで比較するのが現実的です。
そのうえで、PlaudNoteはかなりバランスの良いポジションにいると感じています。
なお、他社サービスとの細かい料金や機能比較は日々変化していくので、最新情報は必ず各公式サイトで確認してください。

ここでお伝えしている内容はあくまで一般的な傾向であり、最終的な選定にあたっては、公式情報と自社のポリシーを照らし合わせながら判断してもらえると安心です。
PlaudNoteは使えないのか
「情報漏洩が怖いならPlaudNoteは使えないのでは?」という極端な意見もありますが、私の感覚としては、これはかなり言い過ぎです。
むしろ、「何も考えずに何でも録音してしまう使い方」さえ避ければ、かなり有力な選択肢になり得ると感じています。
「使えない」と言われがちな理由
- 中国拠点がある=危険と短絡的に結びつけられがち
- AIやクラウドという言葉から「中身が全部覗かれている」というイメージを持たれやすい
- そもそも情報セキュリティのリスク評価が難しく、不安だけが先行しがち
- 「録音してはいけない会議」で使ってしまった事例への不安(実際には運用の問題)
こうした不安は、ツールそのものというより、「使い方のルールが決まっていない」「情報が整理されていない」ことが原因になっていることが多いです。
PlaudNoteを使うかどうかの前に、「自分たちの情報の守り方」を決める必要がある、と言い換えてもいいかもしれません。
それでも私が「使える」と判断している理由
- クラウドをオフにすればローカル完結で使える柔軟性がある
- 端末・アカウントの紐づけや暗号化など、基本的なセキュリティ設計は押さえている
- 利用シーンと情報の機密度を選べば、リスクとリターンのバランスが取れる
- 録音→文字起こし→要約の流れがスムーズで、議事録作成の負担を大幅に減らせる
逆に言うと、「どんな情報も何も考えずに全部PlaudNoteに放り込む」ような使い方をするなら、確かに「使えない」と言わざるを得ません。
ツール以前に運用の問題です。
ここだけは勘違いしないようにしたいところです。
だからこそ、この記事で書いてきたような線引きと運用ルールを決めたうえで、「使うところはしっかり使う」というスタンスが現実的だと考えています。

あなたが「これは録音しても大丈夫そうだな」と判断できる領域を広げていくことが、最終的には生産性アップにもつながっていきますよ。
企業導入時に確認すべきこと

企業としてPlaudNoteを導入する場合、個人利用よりも一段シビアな目線でチェックすべきポイントが増えます。
ここでは、私が企業相談を受けたときによくお伝えしている観点をまとめておきます。
ここを押さえておけば、「後から法務や情シスに怒られる」という悲しい展開はかなり防ぎやすくなるでしょう。
最低限確認しておきたい項目
- 情報セキュリティポリシーで、クラウド録音や外部AI利用が許可されているか
- どのレベルの業務情報までPlaudNoteで扱ってよいか(レベル分けしたルール化)
- クラウド同期オン/オフのポリシー(部署や用途ごとに変えるか)
- 退職・異動時にアカウントとデバイスをどう扱うか(権限剥奪やデータ削除の流れ)
- ログ保存期間やデータ削除手順を誰が管理するか(責任者の明確化)
これらは「セキュリティチェックリスト」というより、「社内ルールとしてどこまで決めておくか」という話に近いです。
特に、クラウド同期の扱いとデータ削除手順は、導入前に決めておかないと、後から現場と情シスが揉めやすいポイントです。
おすすめなのは、「PlaudNoteの利用ガイドライン」を社内セキュリティポリシーの一部として明文化し、導入前に必ず情シス・法務・現場メンバーで合意を取っておくことです。
これだけで「なんとなく不安だからNG」というブレーキをかなり減らせます。
また、医療・金融・公共機関など、特に規制が厳しい業種では、PlaudNote側のセキュリティ認証(SOC2やISOなど)の範囲と、自社のコンプライアンス要件が噛み合うかどうかも確認しておきましょう。
必要であれば、メーカーに追加のドキュメントやホワイトペーパーを問い合わせるのも一つの手です。
最終的な導入可否や運用ルールの決定は、必ず自社の情報セキュリティ担当や専門家と相談したうえで行ってください。

ここを個人の判断だけで進めてしまうと、後から「なぜ事前に相談しなかったのか」という話になりかねないので、慎重なくらいでちょうどいいと思います。
PlaudNoteの情報漏洩と賢い使い方の結論
最後に、PlaudNote情報漏洩のリスクを抑えつつ、セキュリティと生産性のバランスを取るための「賢い使い方」をまとめておきます。
ここまでの内容を実際のアクションに落とし込んだ「チェックリスト」だと思って読んでもらえると嬉しいです。
今日からできる実践的なチェックリスト
- スマホ・PCの画面ロックとパスワード/生体認証を必ず有効にする
- PlaudNoteのクラウド同期設定を見直し、必要なときだけオンにする
- 録音前に参加メンバーへ録音とAI利用の旨を伝え、同意を得る
- 機密度の高い会議は、そもそもPlaudNoteで録音しない
- 利用をやめるときは、クラウドと端末のデータをきちんと削除する
また、外出が多い方はPlaudNotePinとAppleの探す機能を組み合わせて紛失対策をしておくと、物理的なリスクをかなり減らせます。
どれだけクラウドが安全でも、「そもそもデバイスをどこかに置き忘れる」というヒューマンエラーはゼロにできないので、ここは素直にテクノロジーの力を借りていきたいところですね。
PlaudNoteをどれだけうまく使えるかは、ツールよりも「自分たちがどこまで気を配れるか」によって決まります。
なんとなく使うのではなく、「ルールを決めて使う」ことが、最大のセキュリティ対策です。
ここまで読んでいただければ、PlaudNoteの情報漏洩やセキュリティに関する不安は、かなり整理できたのではないかと思います。
私の結論としては、以下のようなスタンスです。
- PlaudNoteは、きちんと使い方とルールを決めれば、おすすめできるAIボイスレコーダー
- ただし、最上位レベルの機密情報や法的にセンシティブな情報は乗せないほうが無難
仕様やポリシーはアップデートされる可能性もあるので、正確な情報は必ずPlaud公式サイトやプライバシーポリシー、利用規約を確認してください。
あなたの使い方次第で、PlaudNoteは「怖いツール」にも「心強い相棒」にもなり得ます。
その舵取りを、この記事が少しでもお手伝いできていたら嬉しいです。
6ヶ月で全世界5万ユーザー&12億円売り上げAIボイスレコーダー PLAUD NOTE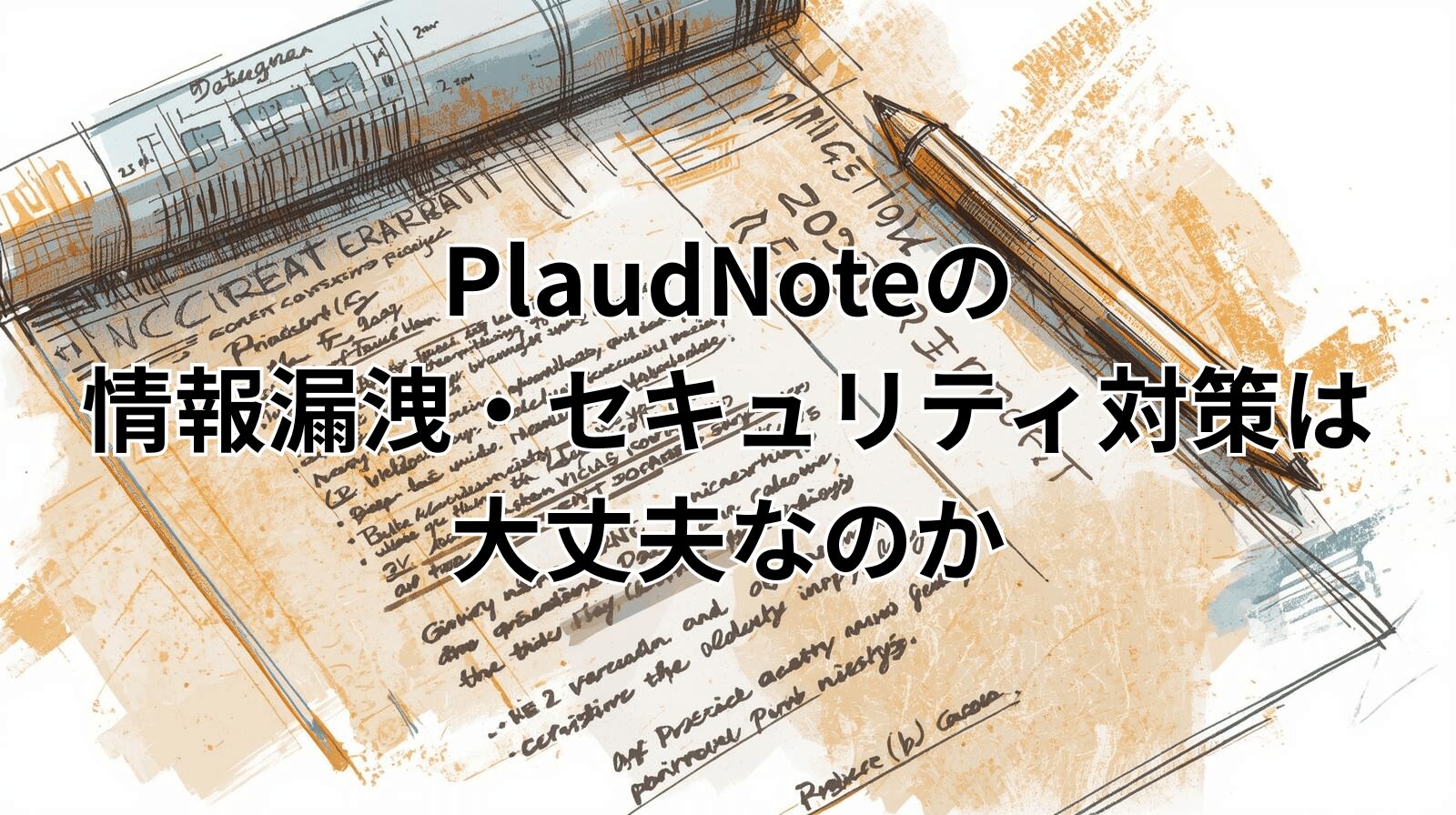



コメント