「Gemini CLIって何ができるの?」
「どう始めればいいの?」
そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
Gemini CLIは、Googleが開発したAI開発者向けのコマンドラインツールで、
テキスト生成やコード補完が可能で、画像解析などはGemini APIを通じて実行できるのが特徴です。
本記事では、初心者でも理解できるように、Gemini CLIの基本機能・導入方法・使い方・活用シーンをまとめました。
最後まで見れば、Gemini CLIを使い始めるための足掛かりとなるでしょう。

私自身も最初は「CLIは難しそう」と感じていましたが、実際に使ってみると数行のコマンドで驚くほど多くのことができます。
この記事では、初めてGemini CLIを使う方が安心して始められるよう、実体験ベースでまとめています。
- Gemini CLIでできること・特徴・導入方法を初心者にもわかりやすく解説
- 代表的な活用シーンと拡張機能を紹介
- Claude codeとの違いを比較
- 実際の利用者の声や注意点もまとめて紹介
Gemini CLIとは?できることの全体像をわかりやすく解説
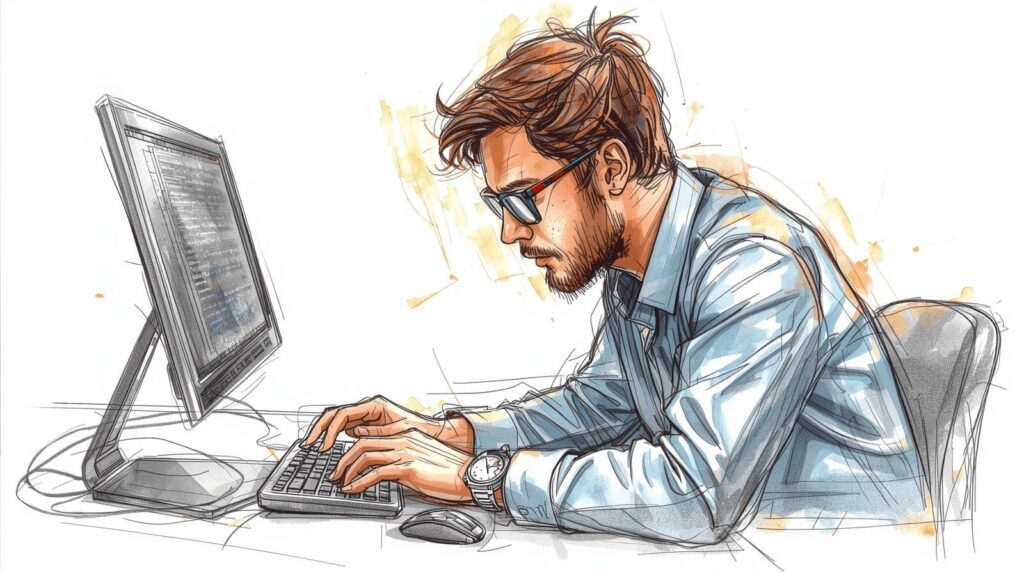
Gemini CLIは、Googleが提供するAIモデル「Gemini」をコマンドライン上で操作できる開発ツールです。
テキスト生成、コード補完、画像解析などをシンプルなコマンドで実行でき、開発効率を大幅に向上させます。
- Gemini CLIの概要と仕組み
- Gemini CLIでできること一覧(テキスト・コード・画像など)
- ReActループとGemini CLIの特徴
- Gemini CLIを使うメリット(拡張性・開発スピード)
Gemini CLIの概要と仕組み
Gemini CLIは、Gemini APIを操作するためのコマンドラインツールです。
補足:コマンドラインとは、文字を入力してコンピュータに指示を出す操作画面(インターフェース)のことです。
マウスやボタンで操作する代わりに、
たとえば次のようにキーボードでコマンド(命令文)を入力します👇
gemini prompt “Hello Gemini!”
このように入力すると、コンピュータが命令を読み取り、結果を表示します。
つまり、コマンドラインとは「文字だけでコンピュータを操作するための画面」
であり、開発者や技術者がAIやプログラムを効率よく扱うためによく使うツールです。
Geminiモデル(例:Gemini 2.5 Pro)は、テキスト、コード、画像、音声など複数のモードを理解できる「マルチモーダルAI」。
CLI(Command Line Interface)を通じて直接AIモデルを呼び出し、対話・生成・解析を高速で実行できます。
つまり、Gemini CLIは、テキストや画像などを理解できるGeminiモデルをコマンドラインから直接操作し、AIによる対話や生成を手軽かつ高速に行えるツールなのです。
- Google公式のCLIツールとしてGeminiモデルを操作可能
- テキスト・画像・コードなどを同時に扱える
- API経由で高精度な生成が可能

最初は「CLI=難しい」と思っていましたが、Gemini CLIは構文がとてもシンプル。
コマンド一行でAIを動かせる手軽さに驚きました。
Gemini CLIでできること一覧(テキスト・コード・画像など)
Gemini CLIでは、テキスト生成・コード補完・画像認識といった多様なAI機能を実行できます。
| 項目 | 内容 | 代表的な使い方 |
|---|---|---|
| テキスト生成 | 質問応答・要約・翻訳 | gemini prompt "要約して" |
| コード補完 | Python・JavaScript対応 | gemini code "関数を最適化" |
| 画像解析 | ファイル指定で説明生成 | gemini vision "photo.png" |
| ファイル要約 | テキストの要点抽出 | gemini file summary report.txt |
- 自然言語とファイル入力の両方に対応
- CLIから直接画像や文書を処理できる
- Google系サービスとの親和性が高い

公式ドキュメントや開発者の投稿を見る限り、テキスト生成からコード補完、画像解析まで幅広く対応しているようです。
特に、コマンド一つで文章と画像を同時に扱える点は魅力的で、今後自分の作業にも取り入れてみたいと感じています。
ReActループとGemini CLIの特徴
Gemini CLIは「ReAct(Reason + Act)」という思考フレームを採用しています。
この思考フレームはAIが推論(Reason)し、実行(Act)を繰り返す仕組みで、単なる生成ではなく“目的達成型の思考”が可能になります。
ファイルを読み取り → 必要な情報を抽出 → コードを出力、といった一連の処理を自律的に実行可能です。
- ReActループで思考と実行を組み合わせ可能
- 単一プロンプトで複数ステップの処理を完結
- 自動化やツール連携に強い構造

「1コマンドで完結する」という体験は本当に快適です。
Gemini CLIを使うと“AIに考えさせる”という概念が自然に理解できます。
Gemini CLIを使うメリット(拡張性・開発スピード)
Gemini CLIの最大の魅力は、拡張性とスピードの両立です。
コマンドベースで動くため、ブラウザUIより操作オーバーヘッドが少なく“速く感じやすく”、その場で検証を回しやすくできます。
特に開発者にとっての利点は以下の通りです。
- 軽量動作:ブラウザ不要で即応答
- 再現性:コマンド履歴から同条件で再実行可能
- 拡張性:ExtensionsやAPIで機能追加が可能
- 軽量で高速なAI開発が可能
- 設定を共有することでチーム開発にも向く
- ExtensionsやMCP対応で機能拡張も容易

Gemini CLIは「使うほどに速くなるツール」です。
一度環境を整えれば、毎日の作業スピードが目に見えて変わるでしょう。
Gemini CLIの導入方法と使い方【はじめての方向け】
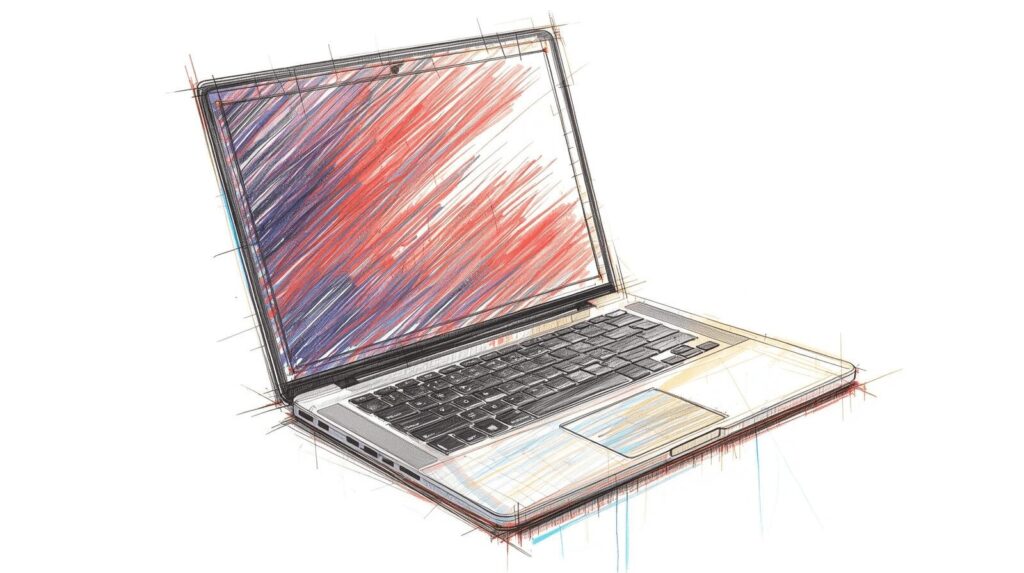
Gemini CLIの導入は思っているよりも簡単です。
この章では、環境構築からインストール、初回実行までを初心者向けに順を追って説明します。
- 利用に必要な環境(Python/Node.jsなど)
- インストール手順(Mac・Windows対応)
- APIキー設定と最初のテストコマンド
- 出力例を見て理解する(Hello Gemini!)
- よくあるつまずきポイント(設定・パスなど)
利用に必要な環境(Python/Node.jsなど)
Gemini CLIを利用するには、次のいずれかの実行環境が必要です。
| 項目 | 推奨バージョン | 補足 |
|---|---|---|
| Node.js | v18以上 | npmでインストール可能 |
| Python | 3.10以上 | pipでライブラリ管理が容易 |
| OS | macOS/Windows/Linux | すべて対応済み |
PythonでもNode.jsでも動作しますが、公式サンプルはNode.js中心で、手順もNode.jsの例が多いです。
補足:Node.jsとPythonの違いについて
Gemini CLIは、どちらの環境でも動作しますが、Node.jsはウェブ開発向けに最適化された実行環境で、Googleの公式サンプルコードもNode.jsベースで公開されています。
そのため、初めてGemini CLIを使う方は、Node.jsをインストールして進めるのが簡単でトラブルが少ないです。
一方、Pythonはデータ分析や機械学習の分野で広く使われており、スクリプトや研究用途でCLIを使いたい場合に向いています
- Node.js 18以上またはPython 3.10以上で動作
- Mac・Windowsどちらも対応
- Google公式はNode.jsを推奨

私はWindows環境でNode.jsを使っていますが、特に問題はありません。
CLI慣れしていなくても、1回設定すればその後は快適に動きます。
インストール手順(Mac・Windows対応)
インストールしたプログラムの実行ファイルを開いてください。
Gemini CLIのインストールは、次のコマンド一行で完了します。
npm install -g @google/gemini-cli
補足:どこで入力する?
このコマンドは、Macの場合は「ターミナル」、Windowsの場合は「PowerShell」または「コマンドプロンプト(cmd)」に入力します。
- Macでターミナルを開く方法:
「アプリケーション」→「ユーティリティ」→「ターミナル」を開くか、Spotlight検索(⌘+スペース)で「Terminal」と入力して起動します。 - Windowsでコマンドプロンプト/PowerShellを開く方法:
スタートメニューで「cmd」または「PowerShell」と入力して検索し、「管理者として実行」を選びます。
いずれも、管理者権限で実行するのがおすすめです。
npm(Node.jsのパッケージマネージャー)が事前にインストールされていれば、そのまま実行できます。
インストール後、バージョン確認で動作チェックを行います。
gemini –version
これでインストールが完了です。
Windowsユーザーは管理者権限で実行するのを忘れずに行いましょう。
- npmコマンドで1行インストール
--versionで動作確認可能- Windowsでは管理者権限が必要

初めてCLIを使う方でも、インストール手順はシンプルです。
私も、思っていたより簡単だったと感じます。
APIキー設定と最初のテストコマンド
Gemini CLIを使うには、Google AI StudioでAPIキーを取得し、環境変数に設定する必要があります。
補足:APIキーの取得方法と設定場所
- Google AI Studio にアクセスし、Googleアカウントでログイン。
- 右上の「APIキー」メニューから新しいキーを発行。
- 発行されたキーをコピーし、以下のように環境変数として設定。
Macの場合(ターミナルで実行):
export GOOGLE_API_KEY=”ここにコピーしたAPIキーを貼り付け”
Windowsの場合(PowerShellで実行):
setx GOOGLE_API_KEY “ここにコピーしたAPIキーを貼り付け”
※PowerShellを「管理者として実行」することで、キーが永続的に保存されます。
Macの場合は、一時的に設定されるため、毎回起動時に再設定が必要です。
恒久設定する場合は、.bash_profile や .zshrc に追記すると便利です。
設定後、テスト実行して動作確認します。
gemini prompt “Hello Gemini!”version
これで、Gemini CLIが正しく動作すれば導入完了です。
- Google AI StudioでAPIキーを発行
- 環境変数にキーを登録
- “Hello Gemini!”で動作確認

初めてAIがCLIから応答したときは、ちょっと感動しました。
“コマンドで会話する”という新しい感覚を体験できます。
出力例を見て理解する(Hello Gemini!)
実際の実行結果は次のようになります。
$ gemini prompt “Hello Gemini!”
Gemini: こんにちは!何をお手伝いできますか?
gemini CLIを導入すると、コマンド入力→AI応答までが一瞬で完了します。
応答の自然さも高く、ChatGPTのような会話体験をCLI上で実現可能です。
- 応答が速く、自然な日本語に対応
- CLIでも会話形式の出力が可能
- 一連の動作を数秒で確認できる

“Geminiから直接返事が来た”という瞬間はワクワクします。
CLIの黒い画面が、まるでAIの対話空間に見えてきます。
よくあるつまずきポイント(設定・パスなど)
Gemini CLIの導入時によくあるトラブルと対処法をまとめました。
導入は数分で終わりますが、PATH設定や権限エラーなど、初期設定でつまずくケースもあります。
ここでは、初心者が実際に遭遇しやすい4つのポイントを整理します。
PATH設定エラー(gemini command not found)
CLI導入後に「gemini command not found」と表示される場合は、PATH(環境変数)にnpmのパスが通っていない可能性があります。
以下のコマンドでインストール状況を確認しましょう。
npm list -g –depth=0
where gemini
(Macの場合は which gemini)
geminiのインストール場所が表示されない場合は、npmのグローバルパスを環境変数に追加してください。
Node.jsを再インストールすると自動で設定されることもあります。
APIキーが保存されない/反映されない
PowerShellで設定したAPIキーが再起動後に消える場合があります。
これは setx コマンドが新しいセッションにしか反映されないためです。
設定が反映されない場合は、PCを再起動するか、新しいPowerShellウィンドウを開いて再試行してください。
環境変数を恒久的に設定したい場合は、システムの詳細設定 → 環境変数から手動で追加することも可能です。
npm installでエラー(EACCES/permission denied)
npm install時に「EACCES」や「permission denied」エラーが出る場合は、権限不足が原因です。
sudo npm install -g @google/gemini-cli
Macでは上記のように sudo を付けて実行、
Windowsでは 「管理者としてPowerShellを実行」 して再試行してください。
これで権限エラーを回避できます。
日本語出力が文字化けする(?????になる)
Windows環境では、出力が文字化けしてしまうことがあります。
この場合は、文字コードをUTF-8に変更することで改善します。
chcp 65001
コマンド実行後に再度 gemini prompt "Hello Gemini!" を試してください。
PowerShellの既定文字コードをUTF-8に設定しておくと、以後の作業がスムーズになります。
よくあるトラブルまとめ
| 項目 | よくある問題 | 対処法 |
|---|---|---|
| PATH設定 | gemini command not found | where gemini でパス確認 |
| APIキー設定 | 再起動でキーが消える | PC再起動 or 新しいPowerShellで再設定 |
| npm install | 権限エラー | sudo npm install -g ... |
| 出力文字化け | 日本語が ??? になる | chcp 65001 を実行 |
- “command not found”はパス設定が原因のことが多い
- APIキー未登録もエラーの一因
- 設定を確認すれば解決できる

Gemini CLIの初期設定は一度クリアすれば安定して動作します。
これらのポイントを押さえておくことで、導入時のトラブルをスムーズに解決できるでしょう。
Gemini CLIでできること一覧【代表的な活用シーン】
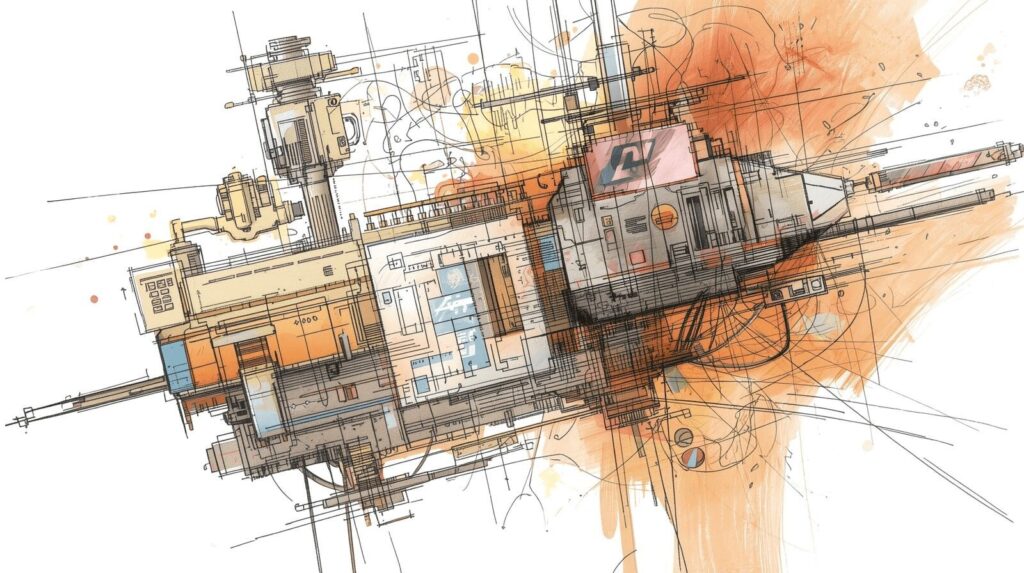
Gemini CLIは、開発・文書作成・画像解析など、幅広いタスクをカバーする“万能エージェント”です。
この章では、実際にどんなことができるのか、活用例を通じて具体的に紹介します。
- コード補完・スクリプト生成
- テキスト要約・文章生成
- 画像解析と説明文生成(マルチモーダル対応)
- ファイル操作やワークスペース支援
- Gemini APIと連携した拡張利用
コード補完・スクリプト生成
Gemini CLIは自然言語からコードを自動生成する機能を備えています。
「Pythonでデータを整形したい」といった指示を入力すると、構文エラーのないスクリプトを即座に作成します。
gemini code “CSVをJSONに変換するPythonスクリプトを書いて”
生成されたコードは実行可能で、必要なライブラリ(例:pandas)を自動で提案してくれます。
初心者でも実務レベルのスクリプト作成がスムーズに実行可能です。
- 自然言語でコード生成可能
- エラーを含まない高精度出力
- 学習や業務効率化に活用できる

利用者の声では「コマンド一行で実行可能なコード提案が得られた」といった報告もあります。
テキスト要約・文章生成
Gemini CLIはテキスト生成タスクにも強く、要約・翻訳・説明文の作成などを一括で処理できます。
以下のような指示で、自然で構造化された文章が即座に出力されます。
gemini prompt “Gemini CLIの特徴を100文字以内で説明してください”
日本語理解の精度も高く、ブログや記事の下書き、資料作成など幅広く利用可能です。
- 高精度な日本語テキスト生成
- 要約・翻訳・リライトも可能
- ChatGPTと比較しても自然な文章構成

私は記事の要約やリサーチ整理に使っています。
書く前にAIに要約を出してもらうと、頭の中が整理されます。
画像解析と説明文生成(マルチモーダル対応)
Gemini CLIは画像入力にも対応し、画像の内容を解析して説明文を生成できます。
以下のコマンドを実行すると、画像内のテキストや構造を分析し、構成要素を言語化して出力します。
gemini vision “design.png” “この画像の内容を説明してください”
プレゼン資料やUIデザインのレビューにも活用可能です。
- 画像内容を文章で説明可能
- デザイン・資料分析に応用できる
- 画像+テキストの同時入力が可能

図表をGeminiに説明してもらうと、見落としていた要点に気づくことがあります。
AIの「客観的な視点」は新しい発見につながります。
ファイル操作やワークスペース支援
Gemini CLIは、ローカルファイルの内容を直接読み取り、要約や変換を行うことができます。
以下のように指定ファイルを読み込ませると、Geminiが要点をまとめて返してくれます。
gemini file summary “report.txt”
Google DriveやGitHubと連携すれば、チームドキュメントの整理にも活用可能です。
- ファイルを直接解析・要約できる
- 他ツールとの連携も可能
- プロジェクト管理の自動化に役立つ

長文レポートをCLIで一瞬で要約できたときは驚きました。
情報整理が“対話”で完結するのは非常に快適です。
Gemini APIと連携した拡張利用
Gemini CLIはAPIと連携し、独自のAIアプリケーションを構築できます。
自作のスクリプトからGeminiモデルを呼び出すことで、AI機能を自分のツールに組み込むことが可能です。
| 活用例 | 説明 |
|---|---|
| チャットボット開発 | Geminiをバックエンドに使用 |
| コード生成ツール | CLI+APIでスクリプト自動生成 |
| 翻訳アプリ | テキスト処理をAIに任せる |
- CLIとAPIを組み合わせて拡張可能
- Geminiモデルを自作ツールに組み込める
- AI連携の第一歩として最適

Gemini CLIでAPIを扱えるようになると、AIの“裏側”が見えてきます。
ただ使うだけでなく、開発にも踏み出せるのが魅力です。
Gemini CLIとClaude Codeの違いを比較
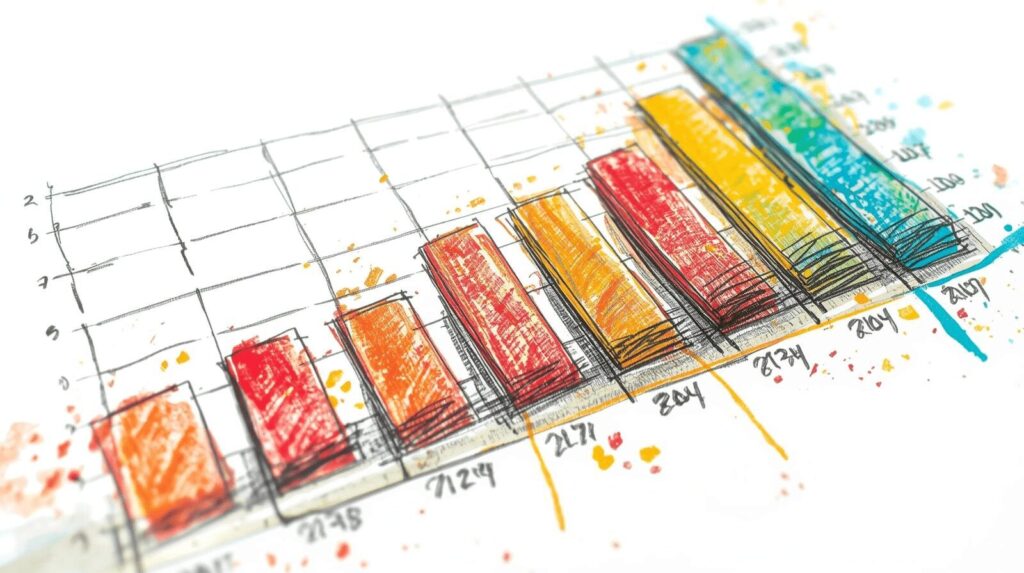
Gemini CLIとClaude Codeは、どちらもAI開発者やライターから注目を集めている高性能ツールです。
一見似ているように見えますが、設計思想と得意領域が大きく異なります。
この章では、両者の特徴や強み・弱み、そして用途別の選び方をわかりやすく解説します。
- Gemini CLI/Claude Codeの比較表
- それぞれの特徴と使い分け
- Gemini CLIの強みと弱み
- 用途別おすすめ(開発・学習・試作)
- 選び方のポイント(目的別マトリクス)
Gemini CLI/Claude Codeの比較表
Gemini CLIとClaude Codeは、どちらもAIによる作業効率化を目的としていますが、「どう使うか」のアプローチが異なります。
Gemini CLIは、コマンドラインからAIを直接操作できる“実行型ツール”。
一方のClaude Codeは、コード理解や長文解析に優れた“思考補助型AI”といえます。
| 項目 | Gemini CLI | Claude Code |
|---|---|---|
| 開発元 | Google DeepMind | Anthropic |
| 中核モデル | Gemini 2.x(マルチモーダルAI) | Claude 3.x(テキスト中心+画像理解対応) |
| 主な操作環境 | コマンドライン(CLI) | エディタやブラウザベース |
| 特徴 | テキスト・画像・コードを横断して処理可能 | 長文要約・設計レビュー・自然対話に強い |
| 強み | 即応性・拡張性・Google連携 | 深い推論力・説明性・自然な表現力 |
| 弱み | 初期設定がやや複雑 | 実行系タスクは非対応 |
| 拡張性 | Extensions/AI Studio連携で拡張可 | Workbench/API連携でのタスク補助が可能 |
| 向いている作業 | 自動化・開発・データ処理 | 設計・レビュー・文書要約 |
両者の関係を一言でまとめると、
「Gemini CLIは“AIを動かす”、Claude Codeは“AIと考える”ツール」といえます。
- Gemini CLIは「コマンドで即実行」、Claude Codeは「対話で深く考える」ツール。
- Geminiはマルチモーダル対応で、画像・コード・テキストを横断的に扱える。
- Claude Codeは長文要約や設計レビューなど、論理的な思考補助に強みがある。

Gemini CLIは“速さと自動化”、Claude Codeは“理解と構成力”。
どちらが優れているというより、作業内容に合わせて切り替えることで、AIを最大限に活かせると実感しています。
それぞれの特徴と使い分け
Gemini CLIは、Googleが提供するCLIベースのAI環境で、ターミナルからAIを呼び出して操作できます。
テキスト要約、コード生成、画像解析などを1行コマンドで実行可能。
「生成→確認→修正→再利用」の流れが非常にスピーディです。
Google AI Studioで作成したテンプレートを呼び出すこともでき、定型タスクの自動化にも適しています。
一方でClaude Codeは、AIによる推論や思考の補助を得意とします。
コードレビュー、設計書の改善提案、長文要約など“考える工程”に強く、説明文の自然さにも定評があります。
思考過程をテキスト化する機能に優れているため、論理的な整合性を重視する作業にも向いています。
- Gemini CLI → 実行・検証・自動化を重視する人
- Claude Code → 思考・設計・レビューを深めたい人

Gemini CLIは“動かすAI”、Claude Codeは“考えるAI”という位置づけで使い分けると、それぞれの強みを最大限に活かせます。
Gemini CLIの強みと弱み
Gemini CLIの魅力は、スピードと拡張性の高さにあります。
ブラウザを介さず、CLI上で完結するため動作が軽く、生成結果を他のアプリやAPIに即座に渡すことも可能です。
また、ExtensionsやMCP対応によって、ユーザー自身がAIの機能を拡張できます。
強み
- マルチモーダル対応で、画像・テキスト・コードを統合処理できる
- CLIベースで動作が軽く、ストリーミング応答が高速
- ExtensionsやAI Studio連携によって、独自機能を追加可能
弱み
- 初期設定(APIキーやパス登録など)に少し手間がかかる
- 抽象的な指示や議論型の推論タスクには不向き
- GUIがないため、初心者には若干ハードルが高い

Gemini CLIは「手を動かすタイプのAI活用」に最適です。
一方で、概念設計や対話的レビューにはClaude Codeの方が優れています。
自分の作業スタイルに合わせて選ぶのがポイントです。
用途別おすすめ(開発・学習・試作)
Gemini CLIとClaude Codeは、それぞれ異なる用途で真価を発揮します。
以下の比較で、自分の目的に合った選択を見つけましょう。
| 用途 | Gemini CLIがおすすめなケース | Claude Codeがおすすめなケース |
|---|---|---|
| 開発 | コード生成・テスト自動化・スクリプト作成 | 設計レビュー・仕様説明・ドキュメント整理 |
| 学習 | 技術資料の要約・翻訳・整理 | 教材作成・リライト・構成提案 |
| 試作 | 自動ワークフローやAPI実験 | 要件定義・設計比較・方針検討 |
- Gemini CLIは「開発や自動化など、手を動かす作業」に強い。
- Claude Codeは「設計やレビューなど、考える工程」で真価を発揮する。
- 2つを組み合わせることで、「実行と推論」を補完し合うワークフローが可能になる。

Gemini CLIは、AIを「動かして理解する」タイプの学習に向いており、
Claude Codeは「考えながらまとめる」作業に強みがあります。
両方を使い分けることで、発想から実行までをAIで完結できるでしょう。
選び方のポイント(目的別マトリクス)
どちらを選ぶか迷った場合は、目的に応じて以下のように判断するのが良いでしょう。
| 判断基準 | Gemini CLIを選ぶべき人 | Claude Codeを選ぶべき人 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 実行・検証・自動化 | 推論・要約・文書化 |
| 作業環境 | ターミナル・API・スクリプト中心 | エディタ・Web UI中心 |
| 重視する点 | スピード・軽量性・拡張性 | 精度・理解力・自然な説明性 |
| 操作スタイル | CLIで直接操作するタイプ | 対話や思考を言語化するタイプ |
- コマンド一行で実行まで完結したいなら → Gemini CLI
- 論理整理や長文構成を磨きたいなら → Claude Code

Gemini CLIは、即時応答でタスクを次々処理したい人に向いています。
Claude Codeは、思考を深めたい人や、設計ドキュメントを正確に整理したい人に最適です。
Gemini CLIをより便利に使うコツと拡張機能
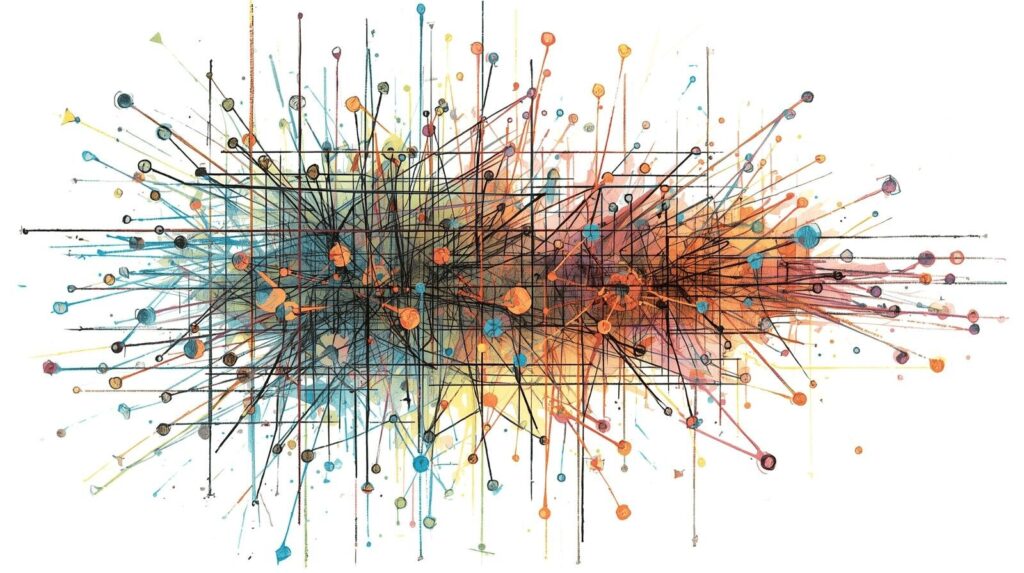
Gemini CLIは、基本操作に慣れたあとで“どこまで広げられるか”が本領発揮のポイントです。
この章では、実務効率を上げるための便利な機能や拡張モジュール、そして応用的な使い方を紹介します。
- 基本コマンドの活用例
- Gemini CLI Extensionsの導入と使い方
- MCP(Model Context Protocol)対応でできること
- AI Studioとの連携で広がる応用
- 作業効率を上げるヒント(自動化・連携)
基本コマンドの活用例
Gemini CLIは、シンプルなコマンド体系で直感的に操作できるのが特徴です。
以下は代表的なコマンドの例です。
| コマンド | 機能 | 使用例 |
|---|---|---|
gemini prompt | テキスト生成・質問応答 | gemini prompt "要約して" |
gemini code | コード生成・最適化 | gemini code "Pythonで関数を作って" |
gemini vision | 画像解析 | gemini vision "sample.png" |
gemini file | ファイル読み込み・要約 | gemini file summary "report.txt" |
これらのコマンドを組み合わせれば、文章作成・開発・分析を一貫して行えます。
特にfileコマンドは、長文資料をAIに解析させる際に非常に便利です。
promptでテキスト、codeで開発支援が可能visionで画像解析も対応- CLIでほぼすべてのAI機能を利用できる

コマンド体系が整理されているので、1〜2日で直感的に扱えるでしょう。
ChatGPTのような自然対話とCLIのスピード感が融合しています。
Gemini CLIの拡張機能導入と使い方
Gemini CLIには「Extensions」と呼ばれる拡張モジュールがあります。
拡張モジュールを導入することで、標準機能を超えた操作が可能になります。
Googleスプレッドシートと連携したい場合は Apps Script や Google Sheets API を介して接続します。
CLIの出力をスクリプトから書き込む構成を試してみてください。
例:CLIの結果をWebhook(Zapier/Makeなど)へPOSTする
gemini prompt “本日の要約を100字で” \
| curl -X POST “https://hooks.zapier.com/hooks/catch/XXXXX/XXXXX” \
-H “Content-Type: text/plain” \
–data-binary @-
例:Node.jsでSheets APIへ書き込む(概要)
▶CLI出力をファイルに保存
gemini prompt “本日の要約を100字で” > summary.txt▶Nodeスクリプト(write_to_sheets.mjs)でGoogle Sheets APIに書き込み
node write_to_sheets.mjs summary.txt
自分でExtensionを開発し、特定の業務タスクを自動化することも可能です。
補足:Extension(拡張機能)とは?
Extensionとは、Gemini CLIに新しい機能を追加できる“拡張モジュール”のことです。
「特定フォルダ内のファイルを自動で要約する」「API経由で他ツールと連携する」といった処理を、自分でExtensionとして開発・登録できます。
ブラウザの拡張機能と同じように、Gemini CLIもExtensionを追加することで、自分の業務や用途に合わせてカスタマイズ可能です。
例:
gemini extensions install summarize-text(要約機能のExtensionを追加)
- Extensionsで外部連携が可能
- Google Sheetsなどのプラグインが充実
- 自作拡張も作れる柔軟設計

私は現時点では拡張モジュールの導入は行っていませんが、
設計を見る限り、業務ごとの自動化やツール連携に大きな可能性を感じています。
MCP(Model Context Protocol)対応でできること
MCP(Model Context Protocol)は、MCP(Model Context Protocol)は、AIツールやモデルを接続するためのオープンな接続仕様です。
Gemini CLIはこのMCPに対応しており、複数のAIモデルを同時に扱うことができます。
例えば、Gemini CLIで要約を作り、その結果を別のAI(例:Vertex AIやPaLM API)に渡すといった連携が可能です。
今後は、1つのCLIコマンドで“複数AIが協力して動く”時代が来るといわれています。
- AI間で情報を共有する新技術
- Gemini CLIはMCP対応済み
- 将来的にはマルチAI環境の中心になる可能性

異なるAIが協調する“連携時代”の入り口に立っている気がします。
Gemini CLIの設計思想が未来志向であることを実感しました。
AI Studioとの連携で広がる応用
Gemini CLIは、Google AI Studioと連携して使うとさらに便利です。
Studioで作成したプロンプトテンプレートをCLIから呼び出し、自動化ワークフローに組み込めます。
gemini prompt –template=”project_summary”
これにより、GUIで設計したフローをCLI操作で高速実行でき、開発・運用の両面で効率化が進みます。
事前に同一Googleアカウントでの認証とAPIキー設定を行う必要がある点は注意してください。
- Google AI Studioとのシームレス連携
- GUI+CLIのハイブリッド運用が可能
- テンプレートの再利用で作業効率アップ

Studioで作ったプロンプトをCLIで動かすと、想像以上に実務的です。
「視覚とコマンドの融合」が実現したツールといえます。
作業効率を上げるヒント(自動化・連携)
Gemini CLIは、他のツールとの連携により活用の幅が広がります。
以下のような以下のようなWebhook/スクリプト連携による自動化を試してみてください。
| 連携ツール | 活用例 |
|---|---|
| Zapier/Make | 生成結果を他アプリへ送信 |
| GitHub Actions | コード生成とテストの自動化 |
| Google Sheets | AI出力の自動記録・整理 |
Gemini CLIはAPIと同様の仕組みで動作しており、
Webhookやスクリプト(Apps Script/各種API)を仲介させて他ツールと連携します。
直接統合ではありませんが、API経由で幅広い自動化が可能です。
例:Zapier Webhookへ要約を送る
gemini file summary “report.txt” \
| curl -X POST “https://hooks.zapier.com/hooks/catch/XXXXX/XXXXX” \
-H “Content-Type: text/plain” \
–data-binary @-
このように“仲介レイヤー”を挟むことで、
Gemini CLIを“AI実験ツール”から“業務フローの一部”に進化させられます。
- Gemini CLIはAPI経由の連携を前提としている
- 直接統合ではなくWebhookやスクリプトを仲介させる
- 開発・分析・レポート作業を効率化できる

私は現在、CLIを日常業務に組み込む構想を立てています。
まだ試行段階ですが、「定型作業をAIに任せる未来」が見えてきた気がします。
Gemini CLIを実際に使ってみた感想と利用者の声
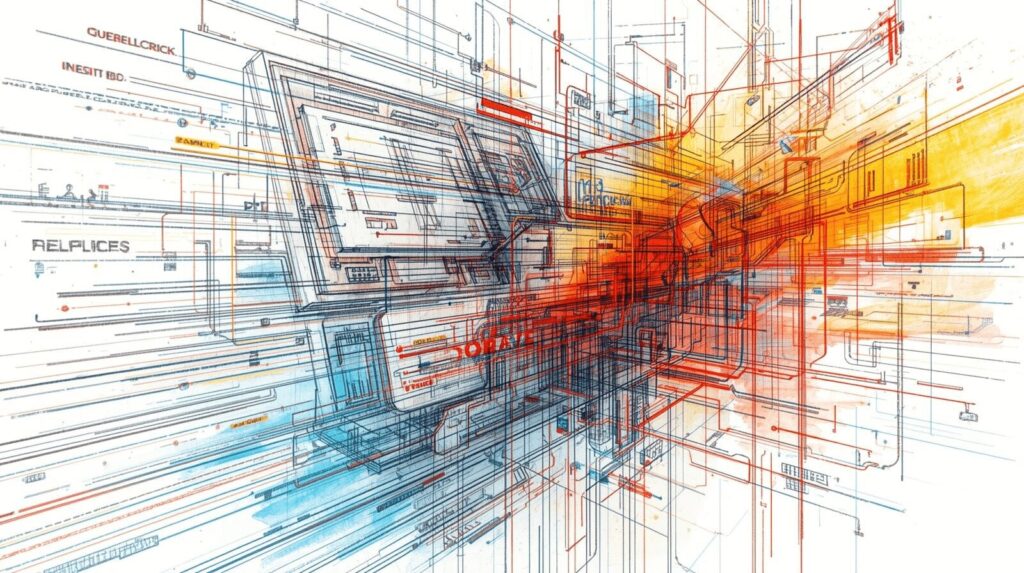
Gemini CLIは、仕様書を読むだけではわからない“実際の体験価値”が多いツールです。
この章では、筆者の利用体験や開発者コミュニティの声を交えながら、リアルな使用感をお伝えします。
- 筆者の体験レビュー(要約・翻訳など)
- 開発者コミュニティでの評判(Qiita・Zennなど)
- 使いやすさ・出力精度の印象
- 初心者が感じたポイント・注意点
- SNSでのリアルな反応まとめ
筆者の体験レビュー(要約・翻訳など)
私はGemini CLIを導入して、AIを使ってレポートの要約や文章の翻訳を効率化を試してみました。
初期のテストでは、英語の学術レポートを要約したり、要約結果を自然な日本語に翻訳する流れを実行しています。
gemini prompt “次の英文を日本語で要約してください:AI agents can plan, reason, and act autonomously.”
返ってきたのは、「AIエージェントは自律的に計画し、推論し、行動できる」という簡潔で正確な要約でした。
文意を損なわず、専門用語を正しく訳してくれて良かったです。
長文をまとめながら翻訳まで行えるため、リサーチ作業のスピードを大きく向上させられそうでした。
- レポート要約と翻訳のどちらも高精度
- 文脈を保ちながら専門用語も正確に処理できる
- CLIから即時応答が得られ、情報整理のスピードが向上

Gemini CLIを初めて使ったとき、その“要約と翻訳の速さ”に驚きました。
これまで別々のツールで行っていた整理・翻訳作業が、一つのコマンドで完結する感覚はとても快適になると思います。
開発者コミュニティでの評判(Qiita・Zennなど)
QiitaやZennといった技術コミュニティでも、Gemini CLIの注目度は高まっています。
特に「VSCodeのターミナルと併用して使うことで、開発の流れに自然に組み込める」という声が増えているのです。
Qiitaの「初心者でも分かる!VSCodeでGemini CLIを使いこなす方法」では、実際にVSCode上からGemini CLIを起動し、開発環境と連携して利用する手順が紹介されています。
また、「Gemini CLIをさっそく試してみた!」では、GoogleアカウントでのログインやAPIキー設定を含む導入体験が詳しく記録されているのです。
さらに、「Gemini CLIの“強み”を知る! Gemini CLIとClaude Codeを比較してみた」では、他のAIツールとの比較を通して、CLI上でAIと対話しながら開発できる点が評価されています。
Zennでも「Gemini CLIの使い方」として、アプリ開発や運用タスク自動化に応用できる可能性が紹介されています。
出典:
Qiita「初心者でも分かる!VSCodeでGemini CLIを使いこなす方法 – インストールから応用まで徹底解説」
Qiita「Gemini CLI をさっそく試してみた!」
Qiita「Gemini CLIの”強み”を知る! Gemini CLIとClaude Codeを比較してみた」
Zenn「Gemini CLI の使い方」
これらの投稿から、Gemini CLIは“開発補助ツール”という枠を超え、開発環境の一部として組み込まれ始めているとかんがえられるでしょう。
- コミュニティでの評価が拡大中
- Googleサービス連携を高く評価する声が多い
- 技術者の自動化ツールとしての導入が進む

Qiitaで共有されているスニペットを参考にすると、CLI操作がさらに楽になります。
実践的なTipsが多く、初心者でも安心して導入できます。
使いやすさ・出力精度の印象
Gemini CLIの操作感はとても軽快で、レスポンスも速いです。
特に、会話形式でタスクを指示できる点が大きな魅力です。
一方で、抽象的な質問に対しては意図を正確に汲み取れない場合もあります。
プロンプトの書き方を工夫することで、安定した出力が得られるようになるでしょう。
- コマンド体系が直感的で覚えやすい
- 出力精度は高く、長文タスクにも対応
- 明確な指示を与えると安定した結果を得られる

Gemini CLIは“思考を言語化する練習”にもなります。
指示が明確なほど精度が上がるので、自然とプロンプト設計が上達します。
初心者が感じたポイント・注意点
Gemini CLIは比較的簡単に導入できますが、最初のハードルは環境設定です。
特に、APIキーの設定やパスの登録を忘れると動作しない場合があります。
ただし、エラーが出た場合もGeminiに「このエラーの意味を教えて」と聞けば解決できます。
AI自身にトラブルを説明させるというのも、他にはない体験です。
- 初期設定ではAPIキー登録に注意
- PATH設定ミスが起動エラーの原因になりやすい
- エラーもGeminiに質問すれば解決可能

私も最初に「command not found」エラーに悩みましたが、Gemini自身が解決法を説明してくれました。
分からないことがあっても、AIに聞けば解決できる場合があります。
SNSでのリアルな反応まとめ
SNS(X/旧Twitter)でも、Gemini CLIに関するポジティブな反応が少しずつ広がっています。
特に、開発者層を中心に「軽快で強力なAIエージェント」という印象を持つ声が多く見られます。
Google公式アカウント「Google AI Developers」では、「軽さ」と「高性能」を両立した設計が強調されています。
開発者アカウントの一つ「SearchDataEng」では、応答をストリーミングで返す仕組みへの評価が投稿されています。
AI関連のニュースアカウント「AITECH.io」も、開発者にとって待望のツールとして紹介しています。
SNSでは「軽快さ」「開発者向けの実用性」「新しい対話体験」への関心が高まっており、
Gemini CLIは公開直後から注目を集めていることがうかがえます。
- Google公式も「軽量かつ強力なCLI」として発表
- ストリーミング応答など技術的特徴が評価されている
- 開発者コミュニティで期待の声が増加中

AIがターミナルで動くという感覚は新鮮で、開発者だけでなくリサーチやライティング分野でも活躍の幅が広がりそうです。
まとめ|Gemini CLIでできることを体験してみよう
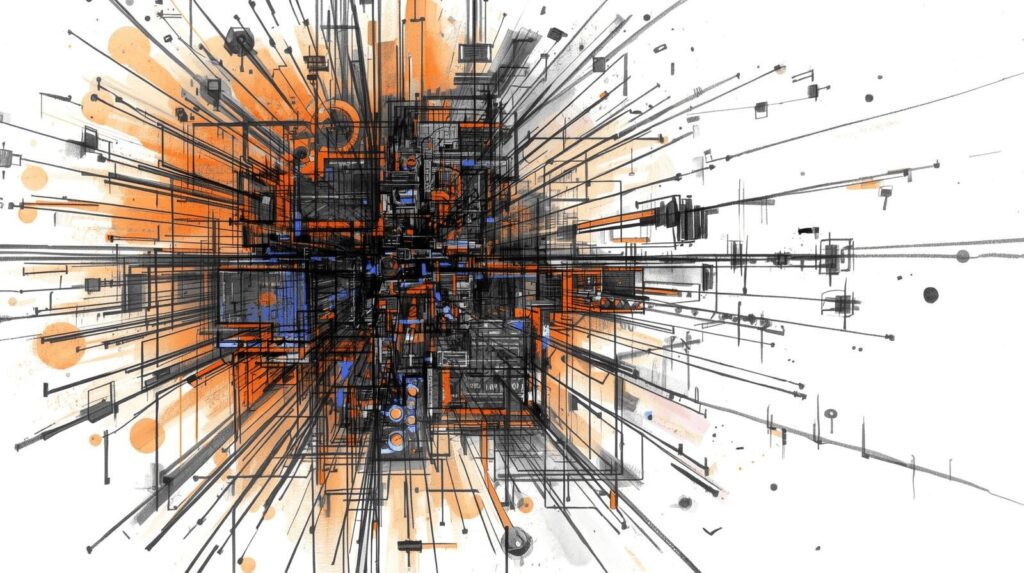
ここまで、Gemini CLIの概要から導入、活用方法、拡張機能、そして実際の体験談までを紹介してきました。
この章では、記事全体の要点を整理し、今後の活用のヒントをまとめます。
- 記事全体の要点まとめ
- Gemini CLIの今後の可能性(拡張・連携)
- FAQ(よくある質問)
記事全体の要点まとめ
- Gemini CLIは、Googleが開発したマルチモーダルAI CLIツール。テキスト・コード・画像を統合的に扱える。
- ExtensionsやMCP対応により、自分専用のAI環境を構築できる。
- 翻訳・リサーチ・開発支援など、実務レベルでの活用が可能。

Gemini CLIを使うと、「考える→作る→検証する」という流れがスムーズにつながります。
開発者だけでなく、ライターや研究者にとっても価値あるAIパートナーです。
Gemini CLIの今後の可能性(拡張・連携)
Gemini CLIは、今後のアップデートでさらなる進化が期待されています。
特に注目されているのは次の3点です。
- MCP(Model Context Protocol)によるAI連携の強化
他のAIモデルと並行実行し、最適な出力を比較できるようになる。 - AI Studioとのリアルタイム統合
GUIで設計したプロンプトをCLIで即実行。プロンプトエンジニアリングが容易に。 - Gemini APIとの完全統合
CLI上で作成したスクリプトをAPIとして呼び出し、自動化処理に利用可能。
- Gemini CLIは将来的に“AI統合プラットフォーム”化する可能性
- 現在もExtensions・API連携が拡大中
- Googleのエコシステムと連動した成長が期待される

Gemini CLIは“AIを動かすツール”から“AIを構築する環境”に進化しています。
学びながら成長するプロダクトとして、今後の展開が楽しみです。
FAQ(よくある質問)
Q1. Gemini CLIは無料で使えますか?
→ 無料枠がありますが、一定以上の利用はAPI課金が発生します(2025年10月時点)
また、Gemini Proモデルなど一部は従量課金制です。
Q2. APIキーはどこで取得できますか?
→ Google AI Studio でログインし、APIキーを発行します。
Q3. 日本語は対応していますか?
→ はい、Gemini 1.5シリーズ以降は高精度な日本語処理が可能です。
(出典:Google AI Developer Docs)
Q4. CLI初心者でも使えますか?
→ 公式ドキュメントに沿って導入すれば問題ありません。
特にWindows・Mac両対応で、手順もシンプルです。
Q5. Gemini CLIはどんな業務に役立ちますか?
→ コード生成、翻訳、資料要約、リサーチなど、AIを使うあらゆる場面で活用できます。
※ 料金や利用制限は変更される可能性があります(2025年10月時点)。
関連記事
【2025年最新】Geminiの消し方|勝手に起動させない安全な削除・無効化ガイド
ChatGPT(GPT-5)で動画を読み込む方法|字幕・音声・NotebookLMを使った最新の実践ガイド
ChatGPTで図面を作成できるのか?GPT-5が変えるAI設計の可能性
ChatGPTの利用中Enterで送信しない方法|誤送信を防ぐ設定と改行のコツ
ChatGPTアプリとブラウザの違い&課金方法を徹底解説【2025年最新版】
【完全ガイド】ChatGPTをログインしないで使うには?無料体験の始め方と安全対策
ChatGPTのチャット引き継ぎ完全ガイド|メモリ機能・要約・プロンプト活用で“続きから話せる”方法を解説
【完全ガイド】ChatGPTに人格を持たせる設定方法とプロンプト例|“キャラ化”で会話がもっと楽しくなる!
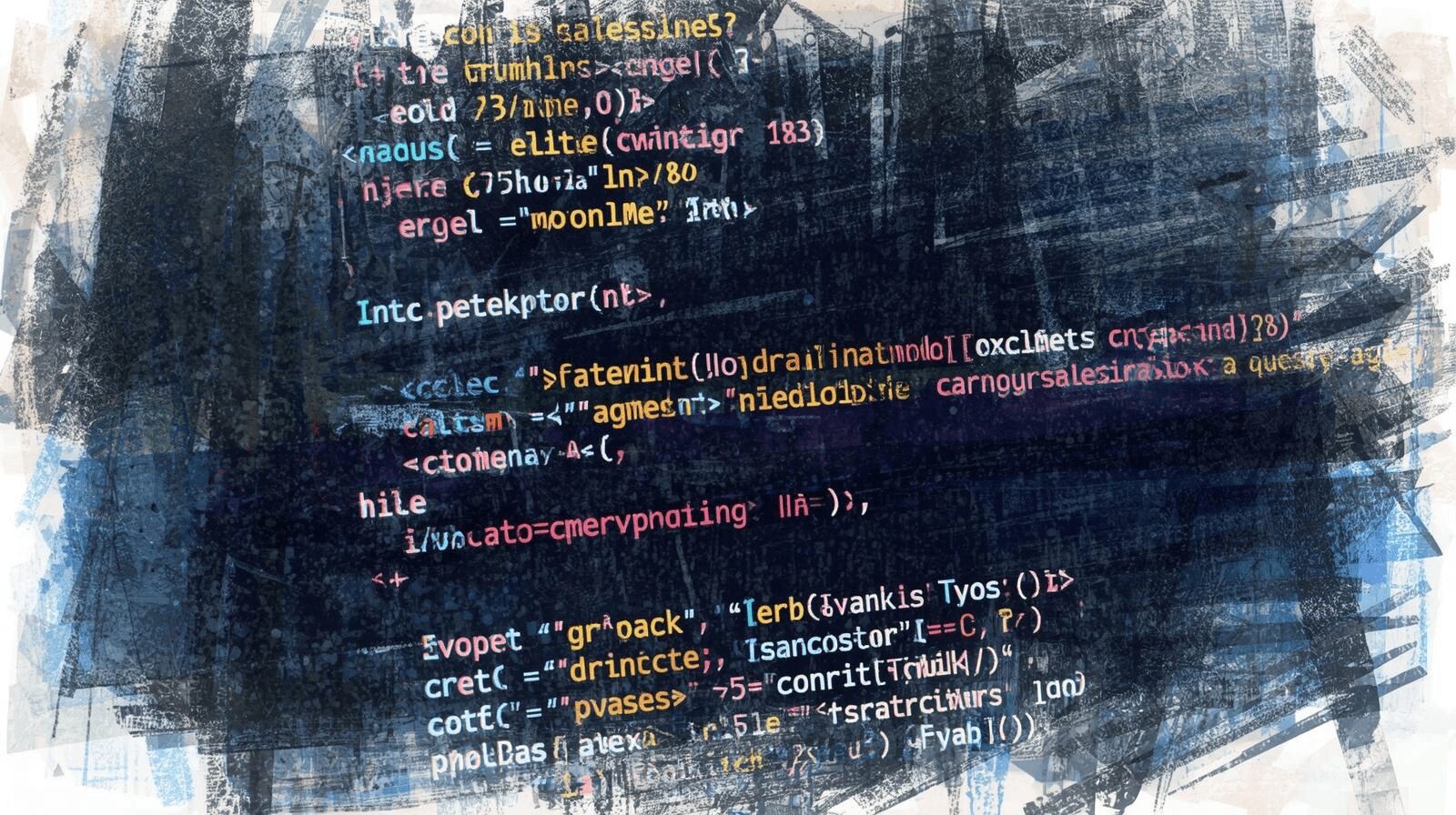


コメント