そう感じて不安になったことはありませんか。もっともらしい説明なのに、数字が違ったり、根拠がなかったり。
実務で使っていると、誤情報に振り回されるのは本当にこわいですよね。
結論から言うと、ChatGPTの“間違いが多い”のは、仕組み上避けられない部分があるためです。
しかし、公的ガイドライン(IPA)でも示されているように、使い方を工夫すれば誤答は大幅に減らせます。
読み終えるころには、「どうすれば間違いを防げるか」がはっきり分かり、安心して使えるようになるでしょう。

私自身、誤情報に気づかず記事を書き直す羽目になったことが何度もあります。でも、原因と対策を理解してからは“誤答を前提に上手に使う力”が身につきました。あなたにも同じ安心を届けられたら嬉しいです。
- なぜChatGPTは誤るのか(仕組み × 公的情報)
- どんな場面で誤答が起きやすいのか
- 精度を上げるためのプロンプト・設定・検証手順
- 安全な使い方(個人情報・業務利用の注意点)
なぜChatGPTは間違いが多いと感じるのか
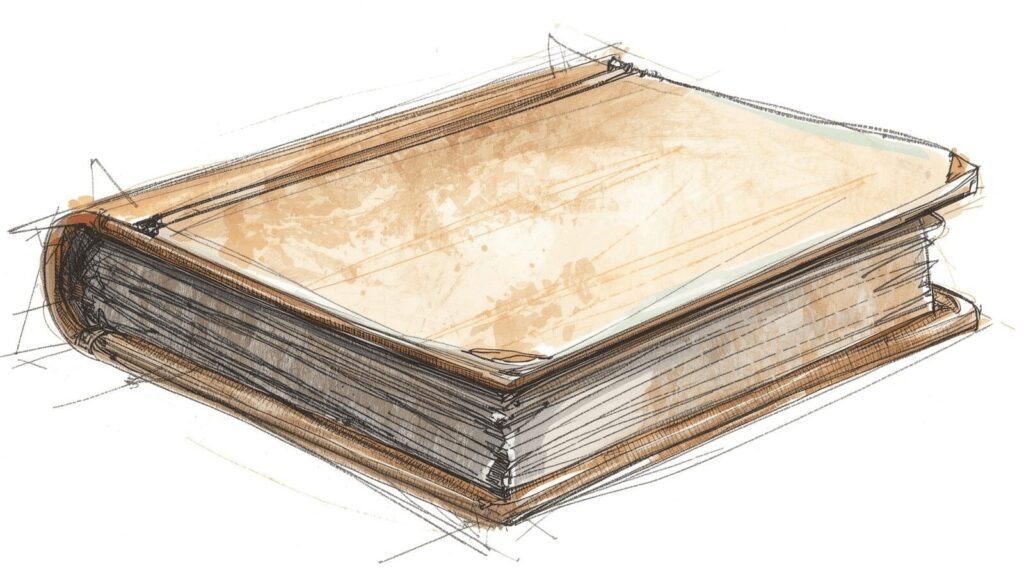
ChatGPTが「最近、間違いが多い気がする…」と感じることはありませんか。
この章では、ChatGPTが誤る理由と限界を整理しつつ、具体的な誤答の起こりやすさを理解するための基礎をまとめました。
- ChatGPTは“事実検索”ではなく“確率的予測モデル”である
- なぜ誤情報(ハルシネーション)が起きるのか
- 間違いが多いと感じる質問の特徴(曖昧・未知領域・断定要求など)
- 「AIは万能ではない」という前提を明確にし不安を緩和する
ChatGPTは“事実検索”ではなく“確率的予測モデル”である
ChatGPTの回答が完璧ではない最大の理由は、そもそも「事実を検索する仕組み」ではないからです。
ChatGPTは、大量の文章データを学習し、次に続く単語を“もっともらしく予測する”仕組みで動いています。
これはGoogle検索とはまったく異なる考え方です。
そのため、「知っていそうな雰囲気で間違う」「根拠を示さず断定する」といった現象が自然と起こります。
OpenAIもハルシネーション(もっともらしいが誤った情報)を「LLMが本質的に抱える特性」と説明しています。
(参考:OpenAI「言語モデルでハルシネーションが起こる理由」)
たとえば、制度名や統計のように“正解が一つしかない情報”ほど、曖昧な推測が入りやすくなるのです。
ここを理解しておくと、“間違いに驚かない姿勢”が持てるようになりますね。
- ChatGPTは“予測モデル”であり、事実の正確性は保証されない
- もっともらしい文章を作るが、情報が正しいとは限らない
- 正確性が求まる場面では注意が必要

私も最初は「検索の延長」と考えて使い、誤情報に振り回されたことがありました。
仕組みを理解した瞬間、ChatGPTとの付き合い方が大きく変わりました。
なぜ誤情報(ハルシネーション)が起きるのか
誤情報(ハルシネーション)が起こる理由は複数あります。
IPA(情報処理推進機構)も、生成AIの特性として「もっともらしい誤情報を出力するリスクは完全に排除できない」としています。
(参考:IPA「テキスト生成AIの導入・運用ガイドライン」)
主な要因は以下です。
- 学習データの偏り
過去のデータに基づいて回答がつくられるため、偏った表現が混ざることがあります。 - 文脈の読み違い
長い会話で前提がズレると、意図と異なる回答をしてしまうことがあります。 - 存在しない情報を補完する挙動
「答えが決まっていない質問」や「曖昧な質問」では、モデルが想像で補完するため誤答が出やすいといわれています。
OpenAI自身も、「LLMが“穴埋め”をしようとすると誤答が生まれやすい」と説明しています。(参考:OpenAI「言語モデルでハルシネーションが起こる理由」)
- ハルシネーションは“仕様上避けにくい”
- データ偏り・文脈のズレ・想像補完が主な要因
- 公的ガイドラインでも「軽減はできるがゼロにはならない」とされる

実務で使っていた時、自信満々なのに間違っている文章が出てきて混乱しました。
今では、ハルシネーションが起きていないかを冷静にチェックできるようになりました。
間違いが多いと感じる質問の特徴(曖昧・未知領域・断定要求など)
誤答が起きるかは、質問の仕方によって大きく変わってきます。
特に以下のような質問は、ハルシネーション率が高まりやすいです。
- 曖昧な質問
「詳しく」「なるべく簡単に」など情報が少ない質問は、推測が増えます。 - 最新情報が必要な質問
ChatGPTの学習データは更新タイミングが限られているため、制度改正・最新ニュースは誤答率が上がります。 - 専門性の高い質問
医療・法律・統計など、引用元が明確でない領域では、ChatGPTは自信ありげに誤った情報を返すことがあります。 - 答えが一つに限られる質問
固有名詞・正確な数字の質問は誤答が特に目立ちます。
IPAのガイドラインでも、曖昧な問いでは不確実性が高まる可能性を指摘しています。
(参考:IPA「テキスト生成AIの導入・運用ガイドライン」)
誤答を回避するために、質問は正確に書くことを心がけましょう。
- 曖昧な質問や“正解が一つの質問”は特に誤答が増える
- 最新情報系は誤りやすい
- 専門領域は“推測”が混ざりやすい

「なんとなく」を含む質問ほど誤答が多いと気づいてから、質問文を整えるクセがつきました。
小さな工夫が精度に大きく影響します。
「AIは万能ではない」という前提を明確にし不安を緩和する
AIは非常に便利ですが、万能ではありません。
生成AIの利用は「人による最終チェック」を前提とされています。
出力が正しいかどうかは、人間の判断が欠かせません。
つまり、ChatGPTを使いこなすために必要なことは、完璧さを期待しすぎないことです。
AIの限界を理解し、必要なところで人が確認する。
これで安定してChatGPTを利用できるようになるでしょう。
- AIは便利だが“正確性が保証されているわけではない”
- 人によるチェックが前提とされている
- 完璧を期待しすぎず“使いどころ”を見極める姿勢が大切

私自身、AIを上手に補助してくれる存在として向き合い、安心して使えるようになりました。
ChatGPTに間違いが多いと言われる典型パターン4選

ChatGPTの誤答には、実は“よく出てくる特徴”があります。
この章では、誤回答が起きやすい場面をパターン別に整理し、どのモデルがどの領域で強みを持つのかを比較していきます。
間違いの背景を知ることで、次の章で紹介する改善策がぐっと理解しやすくなるでしょう。
- 誤答パターン①:もっともらしく語る「虚構生成」
- 誤答パターン②:数字・日付・法律・制度の誤り
- 誤答パターン③:主語あいまい/意図の読み違い
- 誤答パターン④:専門領域での推測回答
- GPT/Claude/Geminiの比較
誤答パターン①:もっともらしく語る「虚構生成」
ChatGPTの誤答で特に特徴的なのが、「自信満々に誤情報を語る」ケースです。
これをハルシネーションと呼びます。
OpenAIは公式に「もっともらしいが誤った情報を生成することがある」と明言しており、ハルシネーションは避けることが難しい特性です。
(参考:OpenAI「言語モデルでハルシネーションが起こる理由」)
このパターンは以下の状況で起きやすいです。
- 存在しない概念へ“ある風”に説明してしまう
- 曖昧な質問を補完して答えようとしてしまう
- あえて知らないと言わず、整った文章として返してしまう
たとえば、「◯◯法案の最新改正内容は?」と聞くと、存在しない改正点を説明してしまうことがあります。
情報を埋めてしまう性質があるため、誤答でも説得力が高い点に注意が必要です。
- もっともらしい誤情報はハルシネーションと呼ばれる
- 曖昧な質問や未知の情報は、埋め合わせで誤答が生まれる
- 出典がないのに断定されることがある

実際、生成AIの回答は文章として自然に読めるため、内容の真偽を見落としてしまうことがあります。
少しずつでも、冷静に見返す習慣を持つことで安心して活用できるようになりますね。
誤答パターン②:数字・日付・法律・制度の誤り
ChatGPTはときどき、数字や日付を“それらしい値”として出力します。
これは、学習データ内の頻出パターンをもとに推測しているためで、正確な数値を返しているわけではありません。
とくに誤りやすいのは以下の内容です。
- 法律・制度・手続きの年号
- 統計データの数値(最新値)
- 報道・ニュースの時期
- 行政の名称・担当部署
公的資料を参照する際には、内容が正しいかの確認を忘れずにしましょう。
- 日付・数字・法制度は誤りやすい
- “断定的な数字”が正しいとは限らない
- 公的資料との照合は必須

記事を作成するとき、ChatGPTの数字を信用して書き進めて後で全部書き直した経験があります。
必ず元データをチェックする。
この習慣で誤情報を防止できるでしょう。
誤答パターン③:主語あいまい/意図の読み違い
ChatGPTは文脈を読むのが得意ですが、主語が省略された日本語では“読み違い”が起こりやすくなります。
たとえば「これについてどう思う?」の“これ”が何を指すのか曖昧なとき、誤った対象について話し始めることがあります。
読み違いが発生しやすいケースは以下のとおりです。
- 直前の話題が複数ある
- 主語や対象が文章内に明記されていない
- 会話が長くなり、前の文脈を誤認する
IPAガイドラインでも「曖昧な質問は不確実性が高まる」と指摘されています。
(参考:IPA「テキスト生成AIの導入・運用ガイドライン」)
- 日本語特有の主語省略で読み違いが起きやすい
- 会話が長くなるほと意図がぶれやすい
- “対象を明記する癖”で防ぎやすくなる

私も「その件は…」と曖昧に聞いたせいで話がかみ合わなくなったことがありました。
相手に伝えるのと同じで、“誰が・何を”を丁寧に書くと精度が上がると感じています。
誤答パターン④:専門領域での推測回答
法律・医療・金融など、専門知識が必要な領域では誤答率が高くなる傾向があります。
これは、細部まで正確さを求められる領域ほど“推測”が混ざりやすくなるためです。
専門領域で誤答が出やすい理由は以下の通りです。
- モデルが専門家レベルの判断を持っているわけではない
- データの“偏り”が再現されることがある
- 言い切るように文章を整えてしまう
特に医療や法律は、誤った情報が重大な影響を与えるため、公的資料の参照や専門家の監修が必須といえるでしょう。
- 専門領域ほど推測が入りやすい
- 専門知識の“前提条件”を読み違いやすい
- 公的資料・専門家監修が必須

専門ジャンルの記事では、“合っているようで微妙に違う”回答が出やすく、最初は気づけませんでした。
今では専門資料を横に置くことで安心して進められています。
GPT/Claude/Geminiの比較
ここでは、主要AIモデルを比較し、誤答が起きやすい傾向を整理します。
| 項目 | GPT(最新) | Claude | Gemini |
|---|---|---|---|
| 正確性 | 高いが、曖昧質問に弱い | 論理性に強く誤読が少なめ | 情報検索に強く最新性が高い |
| ブラウジング | 標準的 | やや弱い | 強い(Google検索の統合) |
| 論理性 | 強め | 特に強い | 場面により揺れがある |
| 文脈保持 | 安定 | 長文に強い | 長文でぶれることがある |
※この比較はあくまで“傾向”であり、必ずしも特定モデルが常に正確というわけではありません。
- GPTはバランス型、Claudeは論理・読解が強い
- Geminiは最新性を活かしやすい
- 用途に応じたモデル選択が誤答防止に役立つ

モデルを切り替えるだけで誤答が減った経験があります。
思考が詰まったときは、一度AIを変えてみるのも良い選択だといえるでしょう。
ChatGPTの間違いが多い場面を減らす方法3ステップ

誤答が多いと感じるときは、使い方を少し整えるだけで大きく改善可能です。
この章では、ChatGPTの間違いを減らすための3つの手順を整理していきます。
- STEP1:プロンプト改善(意図を明確に伝える書き方)
- STEP2:モデル選択と設定で精度を上げる
- STEP3:誤情報を“見抜く”チェックリスト
STEP1:プロンプト改善(意図を明確に伝える書き方)
ChatGPTの精度を上げる最初のポイントは、「相手に誤解されにくいプロンプトを書くこと」です。
曖昧な表現が多いほど、AIは“推測”で補おうとするため誤答が増えます。
逆に、条件・目的・禁止事項を明確にすると、回答のぶれが大きく減ります。
具体的には以下の要素を入れると効果的です。
- 目的の明示:「◯◯を理解したい/比較したい/要約したい」
- 役割付与:「あなたは◯◯の専門家です」
- 条件の固定:「数字は必ず根拠を添えてください」
- 禁止事項:「不明な場合は推測せず『不明』と返してください」
- ステップ要求:「段階的に考えてから結論を出してください」
こうした工夫を積み重ねることで、間違いを減らせるでしょう。
- 曖昧さをなくすと誤答が減る
- 条件・役割・禁止事項の提示が効果的
- プロンプトの設計は、正確な回答のために必須

最初は「どうしてこんなに読み違えるんだろう」と困っていましたが、プロンプトの書き方を変えるだけで精度が変わりはじめました。
少し工夫するだけで、驚くほど改善されるものですね。
STEP2:モデル選択と設定で精度を上げる
ChatGPTが誤りやすい理由は、設定・モデル選択の相性によっても大きく変わります。
ChatGPT・Claude・Geminiなど、モデルごとに得意分野が異なるため、用途に合わせて切り替えるだけで誤答が減ることがあります。
具体的な改善ポイントは以下のとおりです。
- モデル選択を用途で変える
GPT:文章生成・構成力が安定
Claude:読解力と論理性が強い
Gemini:ブラウジング・最新情報に強い - ブラウジング(ウェブ検索)をONにする
最新データが必要なときは、ブラウジング機能を使うと不確実性を下げられます。 - ファイルアップロードを活用する
URLやPDFを直接読ませることで、正確に内容を理解できます。 - メモリ機能を適切に使う
長い作業では前提条件が揃い、回答のブレが抑えられます。
用途に応じた適切な設定と組み合わせによって、出力の誤りを減らせるでしょう。
- モデルごとに強みが違う
- ブラウジング・ファイル入力で誤答を防ぎやすい
- 設定を整えるだけで精度が安定する

長い文章の整理や書籍の要約では、モデルによって得意・不得意が分かれることがあります。
用途に合わせてモデルを切り替えるだけでも、作業のしやすさが変わると感じられる方は多いかもしれませんね。
STEP3:誤情報を“見抜く”チェックリスト
どれだけ工夫しても、誤答をゼロにすることはできません。
そこで重要なのが「誤情報を見抜く力」です。
最終チェックを行うだけで、誤情報によるミスを確実に減らせます。
以下は、誤答を見抜くための簡易チェックリストです。
- 数字と固有名詞は公的資料で照合する
厚労省・総務省・IPAなどの一次情報と比べるのが安全です。 - 断定しているのに根拠がない回答は疑う
自信があるように見えても、中身が伴わないことがあります。 - 「出典は?」と尋ねる
根拠を求めるだけで話が明確になります。 - 別モデルにも同じ質問をする
一致しない場合は、内容が曖昧である可能性が高いです。
出力された内容が正しいかどうか、最終チェックを怠らないようにしましょう。
- 数字・固有名詞は一次情報で必ず確認
- 根拠の提示を求めるクセが大切
- 別モデルにも聞き、内容の一貫性を確認

私も何度も“それっぽい誤情報”に振り回されましたが、チェックリストを習慣にしてからは安心して使えるようになりました。
最後に人の目で確認するだけでも、大きな違いが生まれます。
ChatGPTで間違いが多いときの対策まとめ
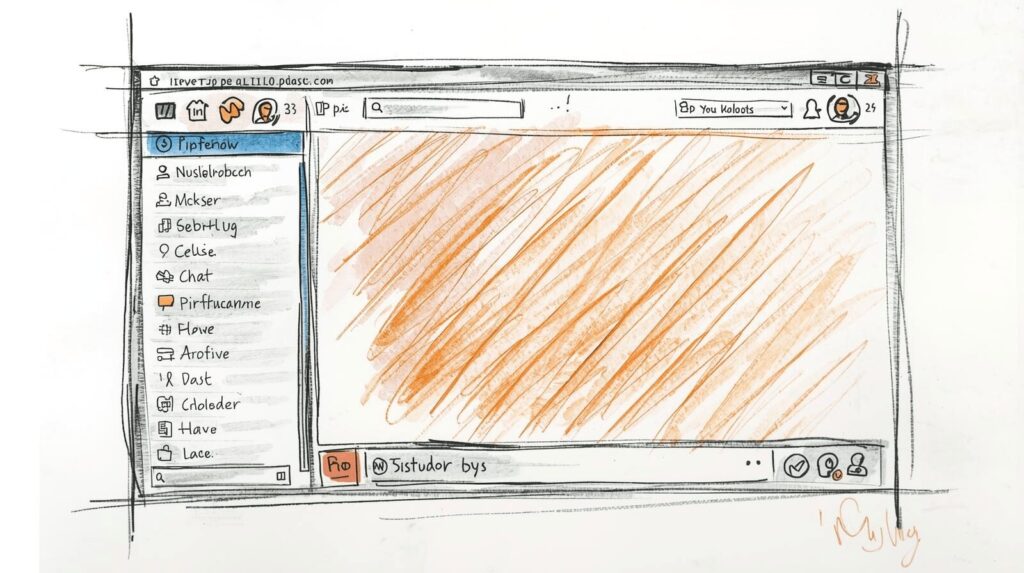
ここまで、ChatGPTが“間違いが多い”と感じる理由から、典型的な誤答パターン、改善方法、安全に使うための考え方まで整理してきました。
この章では、これまでの学びを一度まとめ、読者が「今日からすぐ実践できる行動」に変換していきます。
要点の再掲
■ ChatGPTが間違う原因(仕組み)
- ChatGPTは事実検索ではなく“確率予測モデル”として動く
- 曖昧な質問や未知情報では推測が入る
- もっともらしい誤情報=ハルシネーションが発生する
■ 典型的な誤答パターン
- 自信満々に誤情報を語る
- 数字・年号・制度のズレ
- 日本語特有の主語あいまいによる誤読
- 専門領域の“それっぽい推測”
■ 改善策(3ステップ)
- プロンプトを明確化(条件・役割・禁止事項)
- モデル選択・設定を整える
- 誤情報チェックを習慣化(別モデル照合など)
読者が次に取るべき行動(おすすめの活用ステップ)
- ステップ1:プロンプトを整える
質問を「誰が・何を・どの条件で」に分けて書くと誤答が減ります。 - ステップ2:用途に応じてモデルを切り替える
文章生成はGPT、精密な読解はClaude、最新情報はGemini、といった使い分けが効果的です。 - ステップ3:必ず1回は“冷静にチェック”する
数字・固有名詞は必ず一次情報と照合します。 - ステップ4:長文作業は「メモリ」や「ファイル読み込み」を使う
誤読を防ぎ、精度を安定させやすくなります。 - ステップ5:疑問が残るときは別モデルへの質問で比較
一致しない部分は“不確実”のサインです。
よくある質問(FAQ)
Q1.ChatGPTはどこまで正確ですか?
A.公的機関も「生成AIは誤情報を含む可能性がある」と明言しています。
IPAのガイドラインでは、必ず人が最終判断を行うよう求められています。
(参考:IPA「テキスト生成AIの導入・運用ガイドライン」)
Q2.誤情報を最も簡単に防ぐ方法は何ですか?
A.質問の明確化と、数字・固有名詞の照合です。
「出典は?」と聞くだけでも精度が上がります。
Q3.モデルを変えると精度は上がりますか?
A.用途によっては大きく変わります。
読解・論理性ならClaude、最新性ならGemini、文章生成ならGPTが向いています。
ChatGPTの出力で間違いが多い状況に悩まされている人へ
ChatGPTは完璧ではありませんが、工夫しながら使えば“頼れる相棒”になります。
大切なのは、誤答を恐れるのではなく、誤答の仕組みを理解し上手に付き合うことです。
今日から少しずつ、あなたの作業に合った使い方を試してみてください。
きっと安心して活用できるようになるはずです。
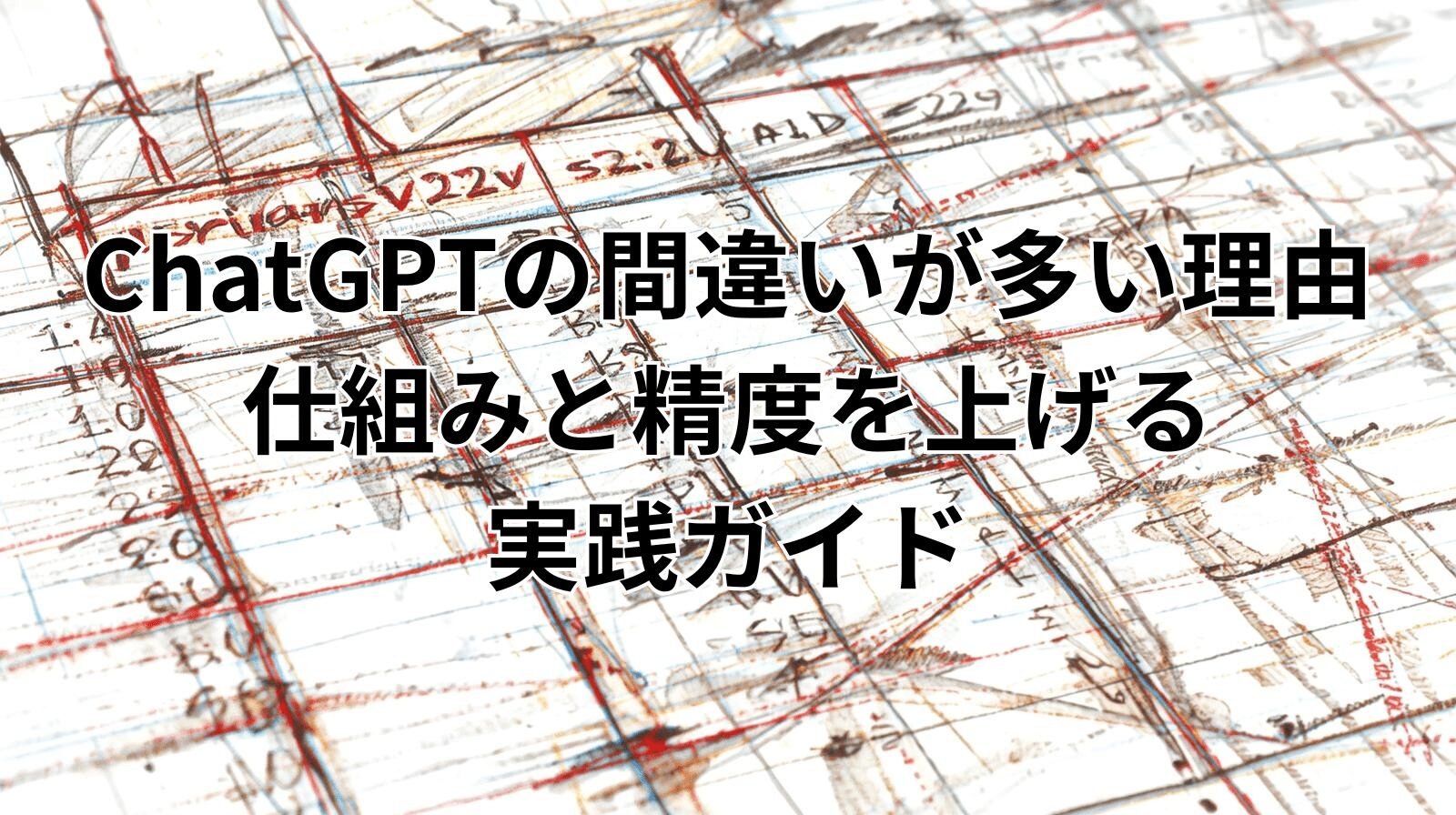








コメント